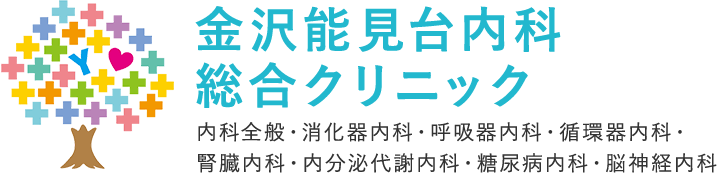脳梗塞などの脳卒中は
再発しやすい病気です
 脳卒中の再発率は、発症後1年で12.8%、5年で35.3%、10年で51.3%というデータがあります。脳卒中を発症した方のうち、2人に1人は10年以内に再発しているとも報告されています。
脳卒中の再発率は、発症後1年で12.8%、5年で35.3%、10年で51.3%というデータがあります。脳卒中を発症した方のうち、2人に1人は10年以内に再発しているとも報告されています。
また、脳梗塞を再発した場合は、初めて発症した時よりも、深刻な後遺症が起こるリスクが高くなるといわれており、再発予防は非常に重要な課題です。
下記のような方は
ご注意ください
- 大量飲酒が常態化している
- たばこを吸っている
- 運動不足
- 肥満
- 味の濃いものが好き
- 高血圧
- 糖尿病
- 心臓病(不整脈など)
当院では診療経験豊富な
神経内科専門医が
長期的なフォローを行います
 当院では、ライフスタイルを重視しつつ、再発予防、症状緩和、後遺症の治療にも力を入れております。脳卒中を再発した際にも、スムーズに治療が開始できるように地域かかりつけ医としてサポートしていきます。
当院では、ライフスタイルを重視しつつ、再発予防、症状緩和、後遺症の治療にも力を入れております。脳卒中を再発した際にも、スムーズに治療が開始できるように地域かかりつけ医としてサポートしていきます。
また、特に脳神経疾患は発症の予防が何より重要です。健康診断などで、高血圧や脂質異常症、メタボリックシンドロームなど生活習慣病を指摘された方、頭痛や肩こりなど気になる症状がある方は、お早めにご相談ください。未病ケアとして数値改善や予防に注力し、脳梗塞などの深刻な疾患を未然に防ぎます。
一部の検査の中には、保険外の自由診療となるものもございますので、詳細につきましてはお気軽にご相談ください。どんな些細な不調や不安についても、お気軽にご相談ください。
脳梗塞(脳卒中)の再発予防に
大切なことは?
脳梗塞は再発リスクの高い疾患ですが、適切に薬を服用し、生活習慣に気をつけることで、再発のリスクを軽減することが可能です。
POINT 1.
生活習慣病の予防・治療
脳梗塞などの脳卒中は、生死に関わる非常に怖い病気ですが、発症を予防できる疾患でもあります。 脳卒中の主な原因は動脈硬化であり、高血圧、脂質異常症、糖尿病などが原因となります。 生活習慣病は症状がほとんどなく、進行が無自覚のままであり、突然発症することがあるため、「サイレントキラー」とも呼ばれています。日頃から早期発見と早期治療を心がけましょう。
1‐①:十分な睡眠をとる、
ストレス発散方法を見つける
睡眠の質や量が低下したり睡眠リズムが不規則になったり、慢性的なストレスを抱えたりすると、生活習慣病のリスクが高まります。それにより、脳卒中のリスクも高まる恐れがあります。
1‐②:禁煙する
タバコにはニコチンや一酸化炭素が含まれており、血圧の上昇や、血液循環の悪化を招く恐れがあります。しかし、たばこの中毒性は強力であり、独力での禁煙はかなり困難です。そのため、ニコチンパッチや禁煙外来など、外部の支援を活用することをお勧めします。
1‐③:高血圧・脂質異常・
糖尿病を指摘されたら
早期に治療を開始する
高血圧は、安静時に測定した値が140/90mmHg以上の状態です。脂質異常は、悪玉(LDL)コレステロールや中性脂肪が基準値より高い、もしくは善玉(HDL)コレステロールが基準値より低くなる疾患です。
糖尿病は、血液中のブドウ糖の濃度が基準値より高くなる病気です。発症すると、脳卒中を含む様々な合併症を引き起こす恐れがあります。
いずれも食事や運動療法をはじめ、薬の服用、値の管理が重要です。
POINT 2.
薬をきちんと服薬する
お薬は、処方された方法と量を守って服用しましょう。途中での中断や自己判断による調整は避けてください。市販薬を使用する際には、まず主治医や薬剤師へ相談してください。
POINT 3.
生活習慣の改善
(食生活・運動機会・睡眠・
ストレス等)
3‐①:脂質異常症を
指摘されたら早期に治療を受ける
悪玉(LDL)コレステロールや中性脂肪が基準値より高い、もしくは善玉(HDL)コレステロールが基準値より低くなる疾患です。このような状態を放置せず、生活習慣の改善や薬物療法を受けることが重要です。
3‐②:減塩で高血圧を予防する
食塩は体内の浸透圧をコントロールし、全身の水分量を調整するという重要な役割を果たしています。摂り過ぎると高血圧の原因となるため、高血圧の患者様は1日1g食塩摂取量を減らしましょう。そうすると、平均1mmHg以上の収縮期血圧の低下が見込まれます。高血圧の方は減塩に併せて、血圧の管理と薬の服用を続けることが重要です。
減塩のコツ
- ・鰹節や昆布など、自然の旨味をうまく活用する
- ・麺類のスープは飲み干さない
- ・香辛料(からし、わさびなど)や香味野菜(生姜など)を活用する
- ・テーブルに調味料は置かない
- ・減塩タイプの調味料を活用する
3‐③:バランスの良い食事を
心がける
主菜と副菜を組み合わせ、肉や魚、卵、大豆製品、乳製品をまんべんなく摂取しましょう。また、野菜や果物、海藻には、高血圧を予防するカリウムや動脈硬化を防ぐのに期待できる抗酸化ビタミンが含まれています。ぜひ積極的に摂取しましょう。
※果物を過剰に摂取すると、高血糖や高中性脂肪血症を招く恐れがあります。食べる時は適量を意識しましょう。
3‐④:過度のアルコール摂取は避ける
お酒を飲み過ぎると血圧が上昇し、脳卒中のリスクが増加します。さらに、アルコールを分解する際に体内の水分が失われると、脱水や脳梗塞のリスクが高まるため、摂取量には注意しましょう。
1日のアルコール摂取目安
- ・日本酒: 1合まで
- ・焼酎 :6合まで
- ・ビール:500mlまで
- ・酎ハイ:500mlまで
- ・ワイン: 180mlまで
3‐⑤:適切な運動を
心がけましょう
脳卒中の発症・再発を防ぐには、身体活動を積極的に行うことが大切です。身体活動とは、運動や日常生活での動きを通じて、エネルギーを使う全ての活動を指します。これにより、次の3つの効果が期待できます。
- 脳卒中の発症リスクが低下します。
- 脳卒中の重症度が軽減されます。
- 発症後の回復が促進されます。
身体活動 目標値(歩数)
- ・20 ~ 64 歳の男性:1日9000歩
- ・65 歳以上の男性:1日7000歩
- ・20 ~ 64 歳の女性:1日8500歩
- ・65 歳以上の女性:1日6500歩
POINT 4.
転ばないための環境づくり
退院して暮らし慣れた自宅に戻るのは、喜ばしいことかと思います。しかし、住み慣れた自宅でも、環境を見直して転倒による再発予防に努める必要があります。ご自身やご家族とよく相談の上、安心して生活できる環境を整えましょう。必要に応じて介護保険を利用し、手すりや福祉用具を設置することもお勧めします。
当院で行う検査
MRI検査などを受けていただく必要性がある場合には、近隣の高度医療機関へ紹介します。
CT検査
 レントゲンを使用し、コンピュータで分析して断層画像を生成する検査です。撮影にかかる時間が短く、脳の部位のみでしたら約30秒で撮影完了します。また、出血や骨、石灰化の検出能力においても優れています。外傷や脳内出血、くも膜下出血の可能性がある場合はCTが、脳梗塞の可能性が考えられる際にはMRIが優先的に行われます。MRI検査が必要と判断された場合には、近隣の高度医療機関に紹介いたします。
レントゲンを使用し、コンピュータで分析して断層画像を生成する検査です。撮影にかかる時間が短く、脳の部位のみでしたら約30秒で撮影完了します。また、出血や骨、石灰化の検出能力においても優れています。外傷や脳内出血、くも膜下出血の可能性がある場合はCTが、脳梗塞の可能性が考えられる際にはMRIが優先的に行われます。MRI検査が必要と判断された場合には、近隣の高度医療機関に紹介いたします。
心電図検査
心臓の動きは微弱な電気によって制御されています。心電図は、この電気の流れを記録する検査です。電気の流れの変化を見て不整脈や虚血の有無を確認します。他にも、階段昇降などの負荷をかけて行う負荷心電図や、24時間常に心臓の状態を観察するホルター心電図などもあります。
心臓超音波検査(心エコー)
 超音波を用いて、心筋の運動や心室を区切る弁の運動などを調べる検査です。検査時間は、検査を行う目的によって若干変動しますが、およそ20〜30分です。患者様は、左側が下になるように横になり、呼吸の状態(吸う・吐く・止めるなど)に合わせて観察されます。
超音波を用いて、心筋の運動や心室を区切る弁の運動などを調べる検査です。検査時間は、検査を行う目的によって若干変動しますが、およそ20〜30分です。患者様は、左側が下になるように横になり、呼吸の状態(吸う・吐く・止めるなど)に合わせて観察されます。
頸動脈超音波検査
脳に血液を供給する、頸動脈を細かく調べる検査です。この血管は、脳への血流を担っているため、頸動脈の動脈硬化が進むと脳血管障害のリスクが高くなります。また、頸動脈の状態を調べるだけで、全身の動脈硬化の程度も推測できます。
下肢静脈超音波検査
足の付け根(鼠径部)から足先にかけての静脈を超音波で観察する検査です。足の血管が皮膚の下から盛り上がるように隆起する静脈瘤や、静脈に血栓が生じる深部静脈血栓症が疑われる際に実施されます。検査は腰を掛けた姿勢、または仰向けになった姿勢で行います。
血圧脈波計(血管年齢検査)
 動脈硬化の進行度を確認する検査です。左右の上腕と足首に巻かれたカフで血圧を計測し、心音を胸部で聴取し、心電図を手首で記録します。
動脈硬化の進行度を確認する検査です。左右の上腕と足首に巻かれたカフで血圧を計測し、心音を胸部で聴取し、心電図を手首で記録します。
動脈硬化は生活習慣病の影響で進行する恐れがあるため、生活習慣病の治療を受けている方は、動脈硬化の状態を定期的にチェックするために血圧脈波検査を受けるのが望ましいです。
ワーファリン血中濃度判定検査
 脳梗塞を含む血栓症を未然に防ぐために、血液をサラサラにするためにワーファリンを服用している方が対象です。
脳梗塞を含む血栓症を未然に防ぐために、血液をサラサラにするためにワーファリンを服用している方が対象です。
血栓症は命に関わるリスクがあるため、ワーファリンの服用は慎重に管理する必要があります。1ヶ月に1回、血の固まりやすさを測定し、現在の服用量の適切さを評価して処方量を調整していきます。当院では外来診察中に即日結果が分かるため、こまめで的確な管理が可能です。