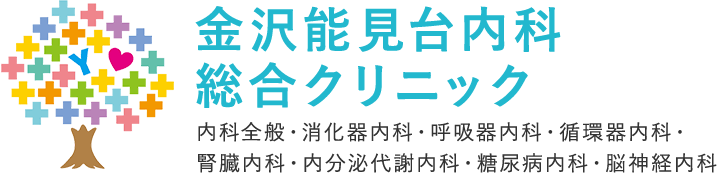狭心症とは
 冠動脈は、心臓を動かすために、酸素や栄養素を送る血管です。
冠動脈は、心臓を動かすために、酸素や栄養素を送る血管です。
狭心症とは、この冠動脈が狭くなり、届けられる血液の量が減った結果、心筋(心臓を動かす筋肉)が酸欠状態に陥る疾患です。酸欠状態により、胸の痛みなどを引き起こします。
一般的な狭心症の原因は、動脈硬化による冠動脈の狭窄です。動脈硬化は、主に生活習慣病の発症によって悪化します。また、冠動脈が痙攣して収縮する攣縮(れんしゅく)によって狭心症になるケースもあります。この場合は、軽度な動脈硬化でも症状が出ることがあり、若い方でも発症する可能性があります。さらに、川崎病の後遺症や大動脈弁膜症の発症を機に、狭心症の症状が出ることもあります。
狭心症の初期症状
- 少し動いただけで動悸が続く
- 眠っていると突然胸が苦しくなる
- 昔よりもめまいや立ちくらみの頻度が増えた
狭心症による胸痛は、圧迫感や灼熱感などといった症状が多く報告されています。これらの症状は、心臓の左側だけでなく、胸の前面、背中、みぞおち、肩、腕、首などでも現れることがあります。また、歯や喉が痛むこともあります。痛みは数分程度で、安静にしていれば改善されるケースが多いです。
狭心症のタイプ別の症状と対処法
労作性狭心症
労作とは、やや激しい運動などを指す言葉です。労作時には心臓が活発に動き、さらに多くの血液が必要となります。安静にしていると痛みが収まる場合、労作性狭心症の可能性が考えられます。例えば、階段や坂道を上ると胸が苦しくなったり、重い物を持ち上げると胸が痛くなったりするような症状が現れます。労作性狭心症の場合、胸の痛みを感じたら、まずは静養しましょう。まずは椅子に座ってから衿元を緩め、呼吸が楽にできるようにしてください。
治療が処方されている場合は、胸痛が生じた際、舌下錠のニトログリセリン(ニトロペン)を口に含めましょう。ニトログリセリンには、冠動脈を拡張させ、心臓の負担を軽減する効果があり、心筋虚血状態を短期間のうちに改善するのに期待できる薬です。
ただし、血圧が低下して倒れるリスクがありますので、もし倒れても怪我をしないよう、椅子に座ってからニトログリセリンを口に含んでください。
安静時狭心症、冠攣縮性狭心症
何もしていないときに胸痛を引き起こす狭心症です。症状は夜間や就寝中、早朝に多く起こります。痛みの性質や発生箇所は、労作時狭心症と似ています。
原因のほとんどは、冠動脈の一時的な痙攣により、血流が一時的に遮断されることです。この状態は攣縮性狭心症とも呼ばれており、動脈硬化によるものと考えられています。
安静時狭心症の胸痛は、舌下錠のニトログリセリン(ニトロペン)によって冠動脈の収縮を緩和し広げることができ、改善効果に期待できます。また、カルシウム拮抗剤も使用されることがあります。
不安定狭心症
狭心症の発作が頻繁に起こり、安静時でも症状が現れる不安定な状態です。「急性冠症候群」とも呼ばれ、心筋梗塞の発作の前触れとして現れることも多いです。さらに、発作を繰り返すことで、心筋梗塞(心臓が壊死する疾患)に移行し、突然死に至る恐れもあります。迅速かつ適切な治療が必要となるため、壊死の可能性がある場合は即座に救急車を要請してください。
微小血管狭心症
狭心症の胸痛発作を引き起こすタイプです。冠動脈の狭窄がないため、誘発試験でも冠動脈が攣縮を引き起こしません。レントゲン血管造影検査では映らないほどの、心筋のごく細い血管が狭窄していると考えられ、この名称が付けられました。状態が悪化するケースはほとんど見られません。
狭心症の診断・検査
患者様から症状を細かく聞いてから診断をつけます。医師は痛みの種類、発生箇所、時期、どれくらい続いたか、軽減された理由などをお伺いします。この問診により、症状が狭心症に関係しているかどうかの初期判断が行われます。確定診断を行うには、複数の検査を行う必要があります。検査は、心臓の健康状態を丁寧に調べ、1人ひとりに合った治療法を提案するために欠かせません。
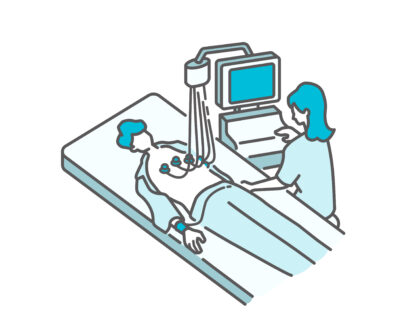 初めに行われるのが心電図(ECG)です。心電図は、心臓の電気活動を記録し、不整脈や過去にあった心筋梗塞の兆候などを検出する検査です。特に狭心症の場合、運動後に異常なパターンが記録されることがあります。
初めに行われるのが心電図(ECG)です。心電図は、心臓の電気活動を記録し、不整脈や過去にあった心筋梗塞の兆候などを検出する検査です。特に狭心症の場合、運動後に異常なパターンが記録されることがあります。
次に実施されるのが運動負荷試験です。トレッドミルや自転車エルゴメーターを使用して、運動中・運動後の心臓の応答を観察する検査です。この試験で心電図に異常が見られれば、狭心症の可能性を疑います。
さらに、心臓の筋肉が損傷を受けると、特定の酵素やタンパク質が血液中に放出されるため、血液検査の結果も重要視されています。これらのマーカーを調べることで、心臓に異常がないかを探ります。
さらに細かく情報を調べるために、心臓のエコー検査(超音波検査)が実施されることがあります。この診断では、心臓の運動や血流状態をリアルタイムでモニターし、心臓弁の異常や心室の機能障害を確認します。
最後に必要とされるのが冠動脈造影となります。冠動脈造影は、造影剤を血管に入れて、レントゲンを使用して冠状動脈の健康状態を調べる検査です。狭窄や閉塞の有無は、治療法の選択において極めて重要な情報となります。造影検査が必要と判断された場合には、近隣の高度医療機関に紹介いたします。
狭心症の治療
薬物療法
心臓の負担を減らすために血管の緊張を和らげ、血流を改善する治療法が実施されます。主に、硝酸薬やカルシウム拮抗薬、交感神経ベータ遮断薬、アスピリンなどの抗血小板薬が使われます。
カテーテル・インターベンション(PCI)・バイパス手術
PCIは、冠動脈の狭窄を内側から拡張するために、カテーテルでバルーン(風船)を膨らませる治療法です。さらに、金属製のステントを留置して再狭窄を予防する場合もあります。ステントの中には、再狭窄を防ぐ薬剤が塗られているDES(薬剤溶出性ステント)もあります。必要に応じて、専門の医療機関にご紹介させていただきます。