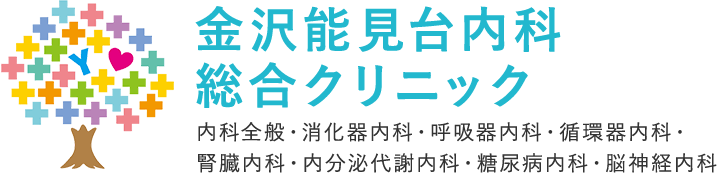気管支喘息とは?
 気管支喘息とは、鼻や口から取り込んだ空気を肺まで運ぶ気道(気管と気管支)にアレルギー性炎症が引き起こされている状態で、長時間にわたる乾いた咳が特徴です。喘息発作の誘因として、風邪や寒暖差、季節の変わり目などが関わることが報告されています。
気管支喘息とは、鼻や口から取り込んだ空気を肺まで運ぶ気道(気管と気管支)にアレルギー性炎症が引き起こされている状態で、長時間にわたる乾いた咳が特徴です。喘息発作の誘因として、風邪や寒暖差、季節の変わり目などが関わることが報告されています。
気管支喘息の症状には日内変動があり、悪化と改善を繰り返し、時には症状がない時もあります。特に夜から明け方にかけて症状が悪化することが多く、喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒュー鳴る)や呼吸困難、咳や痰、胸や喉の圧迫感などの症状が現れます。発作が進行すると、横になっても苦しくなり(起坐呼吸)、血液中の酸素飽和度(SPO2)の低下や意識の混濁が見られることがあります。
気管支喘息の種類別の症状
気管支喘息は2種類に区分されます。
|
アトピー型喘息 |
鼻や口から吸い込まれた埃、ダニ、カビ、花粉などのアレルゲンを吸入してから30分程度のうちに発症する喘息で、即時型アレルギー反応によって起こるタイプです。アレルゲンが見つかると予防しやすくなります。 |
|
非アトピー型喘息 |
感染症やストレス、喫煙などアレルギーとは違った因子によって気道内に炎症反応によって起こるタイプです。炎症メカニズムによって発症すると考えられています。発作がどのような状況で起こるかを把握する必要があります。 |
アスピリン喘息
アスピリンを含むいくつかの鎮痛剤によって引き起こされる喘息発作です。
この喘息の発作は、時に鼻水や目の充血など即時性アレルギー症状にも似ています。さらに、アスピリン喘息は重度の発作が起こり、意識障害を伴うリスクもあります。最悪の場合、命を落としてしまうこともあります。
成人喘息の約10%を占め、男性よりも女性が多く、発症者のほとんどは20~50代の方々です。内服薬や注射に加えて、座薬や湿布薬でも発作を引き起こす恐れがあるため、喘息をお持ちの方は、使用する医薬品にアスピリンが含まれていないかを注意する必要があります。
咳喘息
咳だけが持続する慢性的な疾患です。「ゼーゼー」「ヒューヒュー」という喘鳴や呼吸困難は伴いません。厳密に言いますと咳喘息は喘息の前段階とされており、喘息の一種ではありません。アレルギー素因を持つ方に多く見られ、特に女性は男性よりも発症リスクが高く、再発するリスクも高い傾向にあります。
近年では患者数が急増している疾患の1つです。その原因は不明ですが、風邪、タバコの煙、冷風、会話、電話、運動などが悪化の要因とされています。
さらに、咳喘息の診断は難しく、風邪の後に3週間以上咳が続くか、気管支拡張薬が効いていると判断された場合に、診断されることがあります。
運動誘発喘息
 運動誘発喘息とは、運動により発生する発作のことです。この種の発作は通常、運動を始めてから数分後に発生し、運動を止めると30分程で回復する傾向があります。発作の起こりやすさは運動の形式や継続時間、気温、湿度などによっても異なります。
運動誘発喘息とは、運動により発生する発作のことです。この種の発作は通常、運動を始めてから数分後に発生し、運動を止めると30分程で回復する傾向があります。発作の起こりやすさは運動の形式や継続時間、気温、湿度などによっても異なります。
そのため、運動誘発喘息は喘息の管理が不十分な状態で起こりやすいといわれています。逆に言えば、日々しっかりとコントロールできている場合は、運動誘発喘息が起こりにくくなります。
また、運動誘発喘息が起こりやすいスポーツは、長距離走、サッカー、ラグビーなどの、「野外で行われる競技(ウィンタースポーツも含む)」「運動の強度が強い競技」「持久力が求められる競技」です。一方、運動誘発喘息が起こりにくいスポーツは、水泳や剣道など「室内で行われる競技」「瞬発的な運動が特徴的な競技」です。
気管支喘息の悪化の原因
- アレルギー反応を引き起こす物質(スギやブタクサなどの花粉、埃、ダニ、カビ、ゴキブリなど)
- 風邪、インフルエンザなどの感染症
- 心因性ストレス
- 気圧の変動、季節の変わり目
- 運動
- ペットの飼育
喘息の診断
喘息の診断は、問診や身体的な所見、呼吸機能やアレルギーの検査など総合的なデータを基に行われます。喘息は時間が経つと病状が変わることが多いため、過去に喘鳴や息苦しさを伴う咳がなかったか、既往に小児喘息がないか、風邪後も長引く咳症状がないか、などを丁寧に問診することも重要です。
残念ながら、一度診断された方の95%は根治できないとされています。さらに、一度でも喘息の診断がつけられた方は、保険に加入する時や造影剤・全身麻酔・ワクチン接種を受ける時に、喘息かどうかを申告しなければなりません。このように、喘息の確定診断は、患者様にとって一生涯にわたる重要な問題となります。
当院ではこれらに考慮しながら、臨床的視点だけでなく検査結果も踏まえた上で、喘息の診断を正確に行うよう努めています。
喘息の検査
当院では、血液検査・胸部レントゲン検査などを実施して重症度の確認を行います。
喘息と同じような症状を持つ他の呼吸器疾患との判別や、肺炎などの合併症を知るために行う検査です。必要に応じて、心電図検査や心エコー検査、胸部CT検査などを行います。
喘息の治療
 喘息治療に利用される薬は主に2つあります。1つ目は長期管理薬(コントローラー)で、2つ目は発作治療薬(リリーバー)です。
喘息治療に利用される薬は主に2つあります。1つ目は長期管理薬(コントローラー)で、2つ目は発作治療薬(リリーバー)です。
治療の基本となるのは、気道の炎症を鎮める長期管理薬であり、吸入ステロイド薬によって気道の炎症を軽減する治療と、気管支拡張薬(β2刺激薬、抗コリン薬)による気道拡張治療が実施されます。
アレルギーが関わっている場合は、アレルギーの原因を突き止め、アレルゲンを避ける環境整備も不可欠です。さらに、発作が改善されても、炎症が治まるには時間がかかるため、治療を続けることが重要です。
また当院では、吸入薬の効果を最大限に発揮するために、適切な吸入方法を丁寧に指導しております。喘息治療で十分な効果を感じられない場合は、お気軽に当院をご利用くださいませ。
お子様のアレルギーについて
当院では、お子様の気管支喘息、食物アレルギー、アトピー性皮膚炎、蕁麻疹(じんましん)、花粉症、アレルギー性鼻炎等を診ています。
アレルギーの症状について
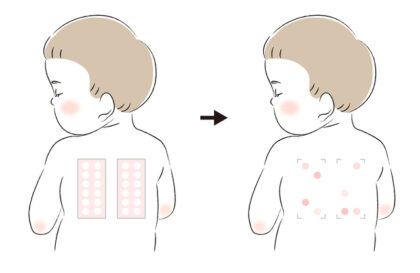 小児アレルギーは、下痢、嘔吐、腹痛、せき、呼吸困難、アトピー性皮膚炎、蕁麻疹(じんましん)、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、発熱、頭痛、むくみ、など様々な症状で表れます。
小児アレルギーは、下痢、嘔吐、腹痛、せき、呼吸困難、アトピー性皮膚炎、蕁麻疹(じんましん)、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、発熱、頭痛、むくみ、など様々な症状で表れます。
よく見られるアレルギーには、食べ物がアレルゲン(アレルギー症状を引き起こす原因となるもの)となる食物アレルギー、ハウスダストなどの吸入性アレルゲンによって発症する気管支喘息などがあります。一方で、成長とともに症状が改善・軽減していくことも多いのが小児アレルギーの特徴です。
小児食物アレルギーで特に赤ちゃん・乳幼児が、アレルギーを起こしやすいのは、卵、牛乳、大豆です。その他にも、カニ、えび、米、そば、ピーナッツ、キーウィ、メロン、マンゴー、ニンニク、セロリなどアレルギーを起こしやすい食べ物はたくさんあります。
また、こどもは気管支や腸管の粘膜などが未熟なため、アレルギー反応を起こしやすい傾向にあります。アレルギーの原因が食べ物以外の環境にあることも考えられます。
アレルギーの原因を特定し、完全に日常生活から除去するのは難しいことです。お子様が何かを口にした際にアレルギー症状が出たため、疑わし食べ物を片っ端から除去するという厳しい食事療法を行う方もいらっしゃいますが、行き過ぎた食事療法は好ましくありません。アレルギーの原因を明確にし、適切な治療を行うことが大切です。
当院では、血液検査や皮膚テスト、検討をつけた食べ物を除いた食事を1~2週間続けて様子を見る除去試験などをして、アレルギーの原因を突き止めます。
様子がおかしいなど、気になることがございましたら、ご相談ください。まず、受診していただき、必要があれば検査を行い、迅速に専門医のいる適切な病院にご紹介いたします。