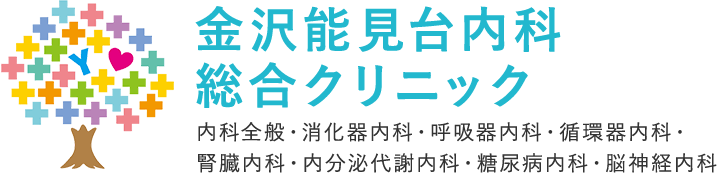咳喘息について
 喘息と同じく、気道の慢性炎症によって引き起こされる咳喘息があります。咳喘息は、通常、喘息の前段階や亜型と見なされ、喘鳴や呼吸困難などの症状は伴いません。症状があっても、咳だけが持続的に現れる特徴があります。季節の変わり目や風邪をひいた後などに、咳が続くことが多い病気で、夜から明け方にかけて悪化しやすく、会話や温度差、タバコの煙などが刺激となり、咳が出やすい傾向が見られます。
喘息と同じく、気道の慢性炎症によって引き起こされる咳喘息があります。咳喘息は、通常、喘息の前段階や亜型と見なされ、喘鳴や呼吸困難などの症状は伴いません。症状があっても、咳だけが持続的に現れる特徴があります。季節の変わり目や風邪をひいた後などに、咳が続くことが多い病気で、夜から明け方にかけて悪化しやすく、会話や温度差、タバコの煙などが刺激となり、咳が出やすい傾向が見られます。
咳喘息の危険な点として挙げられるのは、喘息への移行リスクです。成人の場合、咳喘息にかかった方の約30%が喘息に移行するという報告もあります。吸入ステロイド薬は、この移行率を低下させるのに期待できると考えられています。
このような症状はありませんか
- 咳が長期間(3週間程度)治らずにいるが喘鳴は見られない
- 風邪をひいているわけではないが咳が続いている
- 胸部レントゲン検査で異常を指摘されていない
- 市販の咳止め薬を使っても咳が良くならない
- 就寝前から明け方にかけて咳込む
- 夜になると咳が治まらない
- 気温の変化が大きいと咳が出る
咳喘息の診断
日本呼吸器学会の規定では、咳喘息の診断基準が以下のように定められています。
- 喘鳴を伴わない咳嗽が8週間以上※続いている・聴診上も喘鳴を認めない
- 気管支拡張薬が有効
(※3〜8週間の遷延性咳嗽であっても診断できるが、3週間未満の急性咳嗽では原則として確定診断しない)
この双方を満たす場合に、咳喘息の診断がつきます。
咳が2~3週間続くと体への負担も大きくなりますので、当院では、8週間未満でも治療を進んで行っています。
また、肺がんや肺炎など別の疾患が原因でないかを確認するために、胸部レントゲン検査、呼気一酸化窒素(NO)検査などを受けていただくこともあります。
咳喘息の治療
 咳喘息の診断がついた方に気管支拡張薬を使用すると、ほとんどの方が咳を改善されます。そのため、治療では、吸入薬(吸入ステロイド薬と気管支拡張薬)を用いて気道の炎症を緩和し、気管支の機能を正常に戻す治療が実施されます。
咳喘息の診断がついた方に気管支拡張薬を使用すると、ほとんどの方が咳を改善されます。そのため、治療では、吸入薬(吸入ステロイド薬と気管支拡張薬)を用いて気道の炎症を緩和し、気管支の機能を正常に戻す治療が実施されます。
ただし、治療は薬物療法のみ行うわけではありません。咳喘息の引き金となるアレルゲンを見つけ出し、それを可能な限り回避することも不可欠です。
具体的に言いますと、喫煙者は禁煙を、花粉症の方はマスク着用など、患者様に合わせた治療法を提案しています。
咳に効く食べ物・飲み物
避けるべき食べ物・飲み物
咳(喘息)に効く食べ物や飲み物は?
コーヒー
喘息の治療には気管支を拡張する作用のあるテオフィリン系の薬を使用しますが、コーヒーにも同様の作用が含まれているため、一時的に症状が落ち着くことがあります。ただし、この方法はあくまで喘息発作予防と軽い発作が起こった時の一時的な対策と捉えておくのが良いでしょう。
紅茶
カフェインが含まれているので、喘息に有効だとされております。さらに、リラックス効果のあるハーブティーは発作時に飲むと、心が穏やかになりやすくなります。
ビタミンCやビタミンE、
スルフォラファン
炎症を抑える働きが期待されます。普段から摂取する回数を増やしてみることをお勧めします。
代表的な食べ物
ビタミンC:ミカンや大根、葉野菜など
ビタミンE:緑黄色野菜や黒豆、ナッツ類など
スルフォラファン:ブロッコリースプラウトやブロッコリー
チョコレート
チョコレートには、カフェインとテオブロミンという成分が含まれているため、気管支拡張作用があり、咳を鎮める効果が見込まれます。ただし、テオフィリンなどの喘息発作治療薬を服用している方は、チョコレートの摂取は医師に相談しましょう。
喘息の時に避ける食べ物
刺激が強いものを避ける
強い匂いだけでなく、刺激の強い食べ物も気管を刺激して喘息を悪化させる要因になります。そのため、唐辛子など刺激の効いた香辛料は控えてください。また、強い炭酸飲料や冷たい飲み物は気道の粘膜を刺激して喘息を誘発する恐れがありますので、お酒にも十分注意してください。
アルコール
アルコール摂取により気管支粘膜が腫れるため、喘息が悪化するリスクがあります。もちろん、絶対に禁酒しなければならないというわけではありませんが、飲みすぎには十分気をつけましょう。
気道収縮効果があるものを避ける
ヒスタミンやアセチルコリンには気道収縮効果があるため、それらが含まれているタケノコやホウレンソウ、山芋などはできる限り避けましょう。