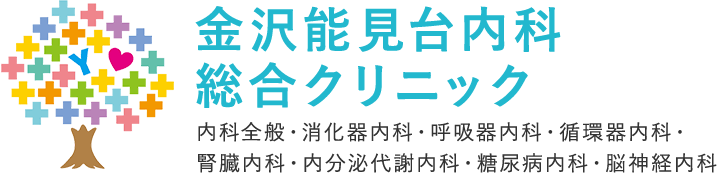糖尿病が疑われる症状
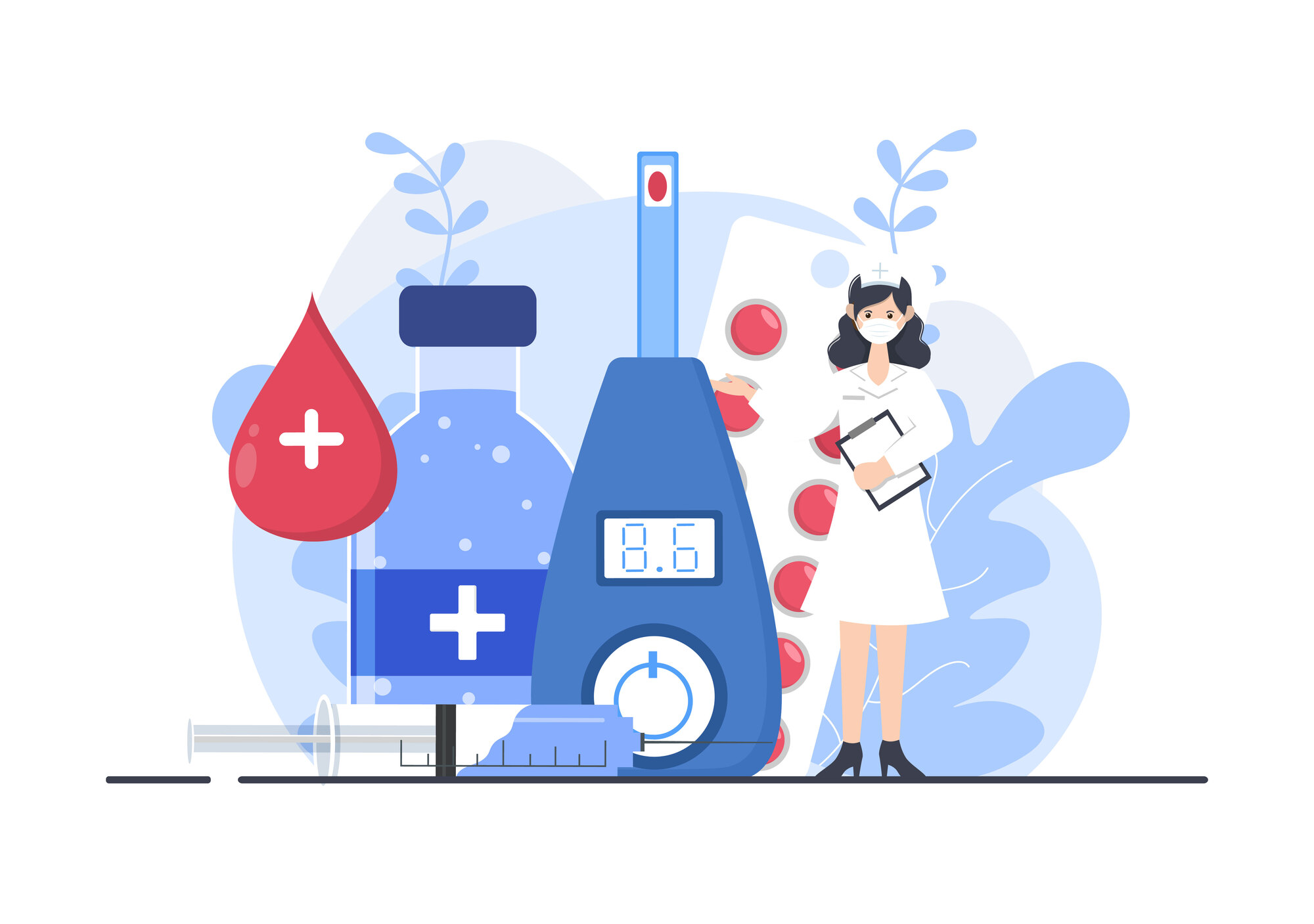 下記の症状は糖尿病の代表的な症状です。他の生活習慣病と同様に、糖尿病は動脈硬化を進行させて心筋梗塞や脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)のリスクを上昇させます。加えて糖尿病では細い血管や神経にダメージを与え、失明・足壊疽、腎不全などを起こす糖尿病網膜症、糖尿病腎症、糖尿病神経障害といった深刻な合併症を発症する可能性もあります。さらに、免疫力を低下させるため感染症の発症・重症化リスクも高くなります。こうした様々なリスクを回避するために、糖尿病は早期発見と適切な治療が重要になります。糖尿病は初期症状がほとんどなく、ある程度進行してから自覚症状が現れますので、少しでも疑わしい症状がある場合には、できるだけ早く受診する必要があります。
下記の症状は糖尿病の代表的な症状です。他の生活習慣病と同様に、糖尿病は動脈硬化を進行させて心筋梗塞や脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)のリスクを上昇させます。加えて糖尿病では細い血管や神経にダメージを与え、失明・足壊疽、腎不全などを起こす糖尿病網膜症、糖尿病腎症、糖尿病神経障害といった深刻な合併症を発症する可能性もあります。さらに、免疫力を低下させるため感染症の発症・重症化リスクも高くなります。こうした様々なリスクを回避するために、糖尿病は早期発見と適切な治療が重要になります。糖尿病は初期症状がほとんどなく、ある程度進行してから自覚症状が現れますので、少しでも疑わしい症状がある場合には、できるだけ早く受診する必要があります。
当院では、糖尿病に関して専門性の高い検査と治療を行っています。下記のような症状のある方、既に糖尿病と診断されたことがある方に加え、健康診断などで高血糖を指摘された方、血糖値に関する不安がある方も、気軽にご相談ください。
- 多飲(のどが渇く・水分摂取量の増加)
- 多尿(尿量や排尿回数の増加)
- 食事や運動は普段通りなのに急な体重減少があった
- 疲れやすい・全身倦怠感
- 目がかすむ
- めまい・立ちくらみ・ふらつきがある
- 手足に痺れ・痛み・冷えがある
- 尿が泡立つ
- 月経異常(生理不順や過多月経など)がある
- 性欲減退 など
糖尿病とは
血液中には全身の細胞のエネルギー源であるブドウ糖が含まれています。このブドウ糖は食事によって増えますが、膵臓から分泌されるインスリンというホルモンによってブドウ糖が細胞に取り込まれることで血糖値は一定に保たれます。
糖尿病は、インスリンの分泌が不足する、または働きが低下することで血糖値が高い状態が続き、全身の細胞がエネルギー不足を起こす疾患です。
糖尿病で慢性の高血糖が続くと全身の血管に大きな負担がかかり、動脈硬化を進行させて心筋梗塞・脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)のリスクが高くなり、細い血管や神経が障害されて深刻な合併症を起こす可能性があります。さらに、糖尿病が悪化すると免疫力も低下し、感染症の発症・重症化を起こしやすくなり、皮膚の傷なども治りにくくなります。こうしたことから、糖尿病は早期発見と治療が重要になります。
糖尿病は1型糖尿病と2型糖尿病に分けられます。1型糖尿病は自己免疫異常によって生じ、2型糖尿病は遺伝的な素因を背景に生活習慣が関与して発症・進行するという違いがあります。生活習慣病とされているのは2型糖尿病であり、日本では2型糖尿病が糖尿病全体の95%を占めているとされています。2型糖尿病は初期症状に乏しく、発見が遅れて深刻な合併症を起こす可能性があります。
厚生労働省が発表した令和5(2023)年の国民健康・栄養調査では、「糖尿病が強く疑われる人は、男性16.8%、女性8.9%」と報告されています。疑わしい症状がある、健診で高血糖を指摘されたなどの場合には、できるだけ早くご相談ください。
金沢能見台内科総合クリニックの糖尿病内科
 糖尿病は、心筋梗塞や脳卒中の原因となる動脈硬化を進行させ、失明・足壊疽、腎不全などを起こす深刻な合併症や、免疫力低下を起こす原因になる疾患ですが、適切な治療を続けて血糖値をコントロールすることでこうしたリスクを抑えることができます。
糖尿病は、心筋梗塞や脳卒中の原因となる動脈硬化を進行させ、失明・足壊疽、腎不全などを起こす深刻な合併症や、免疫力低下を起こす原因になる疾患ですが、適切な治療を続けて血糖値をコントロールすることでこうしたリスクを抑えることができます。
当院では糖尿病の専門的な診療を行っています。現在の状態に最適な治療をご提案し、患者様と相談しながら治療方針を決めています。糖尿病治療で重要となる生活習慣の改善も、患者様のライフスタイルなどにきめ細かく合わせてストレスなく続けられるよう配慮しています。糖尿病は長期に渡ってコントロ-ルが必要な疾患です。当院では患者様に寄り添った治療を心がけていますので、些細なことでも安心してご相談ください。
糖尿病の種類
1型糖尿病
インスリンを分泌している膵臓の膵ランゲルハンス島β細胞が自己免疫異常によって攻撃され、インスリンが分泌されなくなる疾患です。感染症などをきっかけに発症し、幼い子どもや若い世代の発症も珍しくありません。
主な治療法は、不足しているインスリンを注射して補充するインスリン療法です。
2型糖尿病
遺伝的な素因を背景に、過食や運動不足、ストレスなどの生活習慣が関与して発症・進行する糖尿病です。インスリンの効果が落ちるインスリン抵抗性や、インスリン分泌低下を起こしています。
加齢によって発症率が高くなりますが、比較的若い方の2型糖尿病発症が増加傾向にあると指摘されています。日本人を含む東アジア系民族はインスリン分泌能が低い傾向があり、肥満していなくても糖尿病を発症しやすいため注意が必要です。
2型糖尿病の治療
糖尿病は根治に導く治療法はありませんが、血糖値を正常な範囲に維持する治療を続けることで動脈硬化進行や合併症の発症を抑制できます。2型糖尿病では、発症や進行に生活習慣が大きく関与しますので、状態やライフスタイルに合わせた生活習慣の改善は不可欠です。当院では、できるだけストレスを抑えて高い効果を得られる方法を患者様と一緒に考えています。
また、糖尿病になりやすい生活習慣は、高血圧や脂質異常症の発症や進行にも大きく関与します。生活習慣を改善することで、こうした疾患の発症・進行も抑制できます。
妊娠糖尿病
妊娠中に「糖尿病ではないが糖代謝異常がある」ことが発見された場合に診断されます。妊娠前から糖尿病と診断されていた方や、妊娠中に明らかな糖尿病と診断された場合は含みません。妊娠中にはインスリンの効果が落ちやすく、妊娠している方の7~9%に妊娠糖尿病が生じるとされています。放置してしまうと母体や赤ちゃんに様々な合併症を起こすリスクがありますので、適切な治療を受けて血糖値を正常範囲に維持することが重要です。
その他の糖尿病
遺伝子異常や他の疾患、薬の副作用が原因となり、高血糖や糖尿病発症を生じる場合があり、インスリンを分泌する膵臓のβ細胞関連の遺伝子異常や、インスリンの働きを伝える機能に関係した遺伝子異常があって糖尿病を発症することがあります。
他の疾患では、内分泌(甲状腺・副腎・下垂体)疾患、膵外分泌疾患、肝臓疾患、感染症でも高血糖を起こすことがあります。
また、副作用として高血糖を起こすことがある薬には、ステロイドやインターフェロンなどがあります。
原因疾患がある場合や薬の副作用として高血糖が生じている場合には、原因疾患の適切な治療や処方の見直しが必要です。
糖尿病の三大合併症
自覚症状がないと放置してしまうと高血糖が長期間続き、心筋梗塞や脳卒中を起こす動脈硬化を進行させてしまいます。また、高血糖は細い血管や神経にもダメージを与え続けることから、深刻な合併症を起こすことも多いです。
中でも糖尿病の三大合併症と呼ばれている「糖尿病神経障害」「糖尿病網膜症」「糖尿病腎症」は、失明・足の切断・人工透析治療が必要になるといった状態になる可能性があります。
糖尿病は早期の自覚症状に乏しいので、健康診断などで高血糖や糖尿病の疑いを指摘された場合は、できるだけ早く当院までご相談ください。
糖尿病神経障害
神経が高血糖によって障害されて生じます。比較的早い時期に自覚症状を起こしますので、疑わしい症状がないかを確認することが重要です。代表的な初期症状には、手足の痺れ・ピリピリした痛み、冷えなどがあります。外傷やヤケドの痛みを感じにくい、治りが遅いなどで気付くこともあります。進行すると、立ちくらみ・ふらつき、筋力低下・筋肉萎縮、発汗異常、吐き気・嘔吐・下痢といった消化器症状をはじめとした自律神経障害の症状が現れます。さらに進行すると足が痛みや温度を感じられなくなり、足の潰瘍を繰り返して壊疽を起こし、切断に至ることもあります。
糖尿病網膜症
網膜は目の奥に広がり、入ってきた光の刺激を受け取る視細胞が密に存在します。視細胞が受け取った情報を電気信号に変え、視神経を通して脳に送っています。こうした機能を果たすために、網膜には毛細血管が張り巡らされています。高血糖が続くと網膜の毛細血管が障害され、眼底出血や浮腫、網膜剥離などを起こして失明や大幅な視力低下を起こす可能性があります。日本人の中途失明原因として、糖尿病網膜症は緑内障に次ぐ2位であるため十分な注意が必要です。初期の自覚症状がほとんどないことから、深刻な状態まで進行させないために、糖尿病と診断された場合には定期的に眼科を受診してください。
糖尿病腎症
腎臓は血液を濾過して尿を作る機能を担っており、毛細血管が特に豊富な臓器です。高血糖で大きなダメージを蓄積させやすい傾向があり、高血糖が続くと腎臓の機能が徐々に失われ、進行すると腎不全を発症して人工透析や腎移植が必要な状態になります。日本では、人工透析を必要とする原因疾患として最も多いのが糖尿病腎症です。糖尿病治療を受けている場合には、定期的に尿検査や血液検査で腎機能を確認しましょう。
その他の合併症
脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)、心筋梗塞、感染症、下肢閉塞性動脈硬化症、歯周病などの発症・悪化リスクが高くなります。
糖尿病の検査
血液検査を行い血糖値やHbA1cを調べることで、状態を把握します。健康診断でも同様の項目を調べる検査を行っていますので、血糖値やHbA1cで高血糖を指摘された場合には、症状がなくても早めにご相談ください。
なお、糖尿病と診断されたら、治療開始後も血糖値の状態を把握するための検査を定期的に行い、血糖値が正常範囲に維持されているかを確認することが重要です。
血糖値
血液中に含まれるブドウ糖の値を調べる検査です。ただし、血糖値は食事などによって大きく変化します。また、糖尿病でも、血糖値が上がるタイミングが食前に起こる、食後に起こる、その両方で起こるというタイプに分けられ、さらに食事によって急激かつ大幅に血糖値上昇を起こすタイプもあります。適切なコントロールのためにも、空腹時血糖値に加え、食後血糖値を調べることが重要です。
HbA1c
(ヘモグロビン・エー・ワンシー)
HbA1cは赤血球にブドウ糖が結合したもので、この数値は過去1~2ヶ月間の平均的な血糖値と相関することがわかっています。健康診断の血液検査で、HbA1c異常の場合は速やかな受診が必要です。また、5.6%以上は糖尿病予備群とされ、発症を予防する生活習慣の改善が大きく役立ちます。血液検査の血糖値はその瞬間の値しかわかりませんが、HbA1cが高い場合は高血糖の状態がどれだけ長く続いているかを判断でき、血糖値のコントロール状態を把握するためにも有効な検査です。糖尿病の早期発見に加え、治療の効果を確かめ、合併症リスクを判断するためにも重要です。
糖尿病の治療
食事療法と運動療法を行い、それで十分な効果を得られない場合には薬物療法を併せて行います。薬物療法には、内服薬処方とインスリン療法があり、患者様の状態などに合わせて選択されます。
食事療法や運動療法は続かなければ意味がありませんので、当院では患者様ができるだけストレスなく行える方法を一緒に考えています。食事療法は無理なくできる範囲からはじめ、運動もやや早足の散歩を1日30分以上行うなど日常に取り入れやすい内容にすると続けやすくなります。なお、運動療法に取り組むことで筋力が強化されると血行や代謝が改善し、インスリンの働きが向上する効果が期待できます。