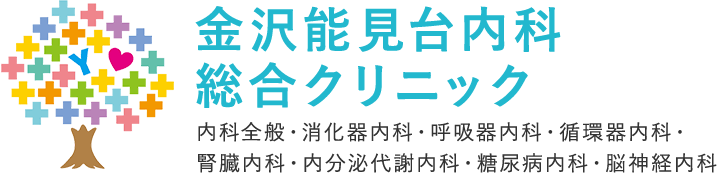下痢について
 下痢は水分を多く含む便です。便の形状や水分量に応じて以下のように分類されます。
下痢は水分を多く含む便です。便の形状や水分量に応じて以下のように分類されます。
形状
バナナ状の便が理想となります。水分が多く泥状の便は「軟便」、さらに水分量が多く水っぽい便は「下痢便」と言われます。
水分量
大腸で吸収された水分量に応じて便の硬さが変わります。水分量が7~8割程度の便が理想で、8~9割程度になると軟便、それ以上は下痢便とされています。
持続期間
下痢は、数時間~2週間で改善する急性下痢と、3週間~4週間以上継続する慢性下痢に大別されます。
受診すべきタイミング
緊急性が高い下痢
- 大量の鮮血便を伴う下痢
- 1時間に1回以上の回数で頻発する下痢
- 38℃以上の発熱や強い腹痛が伴う下痢
- 嘔吐して、水分補給がままならない状態
消化器内科を受診すべき場合
- 1時間に1回の頻度で下痢が続いている
- 下痢が慢性化している
- 便秘と下痢が繰り返し生じる
- 黒いタール便や粘血便が見られる
- 腹痛、吐き気、軽い嘔吐を伴う
下痢の原因
下痢の原因として、香辛料などの刺激物の摂取、暴飲暴食、ウイルスや細菌による感染症、ストレス、炎症性腸疾患、薬の副作用などが挙げられます。
下痢は、便が大腸内部をすぐに通り過ぎるため、水分が十分に吸収されず排出されることで生じます。
下痢の症状
急激な腹痛に伴って強い便意が起こり、1日に泥状便や水様便が何度も繰り返し出るようになります。なお、お腹がゴロゴロ鳴るといった違和感が生じるだけの場合もあります。
原因は便の特徴をもとに特定できることが多いため、診察の際に便の色や形状についてお伝えください。なお、発熱、吐き気・嘔吐、倦怠感などによって脱水症状が長引いている場合は、すぐに当院を受診してください。また、鮮血が混ざった下痢や粘血便が出る場合も、大腸の炎症や潰瘍の可能性があるため、速やかに当院までご相談ください。
急性下痢
急性下痢は、ウイルスや細菌の感染が原因となる急性腸炎によって起こります。急激な症状が起こった場合は、食中毒や暴飲暴食、非感染性腸炎、冷えなどが原因である可能性があります。感染症を引き起こす主なウイルスとしては、ノロウイルス、ロタウイルスが挙げられ、主な細菌には黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌、病原性大腸菌(O-157など)、腸炎ビブリオなどがあります。
慢性下痢
慢性下痢は、下痢が3~4週間以上長引く状態です。主な原因としては、クローン病や潰瘍性大腸炎、大腸がんなどの器質的異常や、腸の運動機能低下や自律神経の乱れによる過敏性腸症候群などが挙げられます。また、ストレスや薬の副作用が原因となる場合や、術後の合併症として起こる場合もあります。
下痢を伴う消化器疾患
食中毒・感染性腸炎
ロタウイルス、ノロウイルス、腸炎ビブリオ、サルモネラ菌、黄色ブドウ球菌、O-157などの病原体への感染が原因となる下痢です。発熱や嘔吐の症状が起こる場合もあります。
過敏性腸症候群
過敏性腸症候群は、器質的異常が発見できないのにもかかわらず、便秘と下痢が繰り返し生じる疾患です。発症原因は、腸の蠕動運動の低下や自律神経の乱れです。症状に応じて、便秘型・下痢型・混合型・分類不能型に分けられます。
潰瘍性大腸炎
大腸粘膜で炎症が生じ、腹痛や下痢、血便の症状が生じます。発症原因は明らかになっておらず、完治できる治療法が見つかっていないため、難病指定を受けています。強い症状をきたす活動期と、症状が治まる寛解期を繰り返します。
大腸ポリープ・大腸がん
発症初期の大腸ポリープ・大腸がんは、自覚症状が乏しいとされています。なお、進行して腸管が狭窄し、便が通る時に擦れて出血すると、血便が生じることがあります。
下痢の診断・検査
問診で下痢の色や形状、回数、発症時期、日々の生活習慣などを丁寧に確認し、その後適切な検査を実施します。
急性下痢
食中毒の恐れがあれば、下痢を引き起こす細菌やウイルスを最優先で突き止めるために検便、炎症の程度などを確認するために血液検査を行い、それらの結果をもとに診断します。
慢性下痢
問診で丁寧に患者様のお話を聞いてから、大腸カメラ検査や血液検査を行います。大腸カメラ検査は、大腸粘膜の状態をリアルタイムで確認し、大腸がんや炎症性腸疾患などの確定診断に繋げます。これらの疾患の発症者数は年々増加しており、早期発見・早期治療が大切です。お悩みの症状があれば、なるべく早めに当院までご相談ください。
下痢の治療
下痢の症状が改善していない場合は脱水を防ぐための水分補給が必要です。
また、以下のように急性下痢と慢性下痢で適切な治療が異なります。
急性下痢
十分に水分補給を行い、必要に応じて点滴なども実施します。また、消化しやすい食事を少量に分けて食べ、抗菌薬や整腸剤を使った薬物療法を実施します。
なお、市販の下痢止めを使用してしまうと病原体を体の外に出せなくなり、かえって症状が悪化する可能性があります。医師の指示を守って服用しましょう。
慢性下痢
病気によって下痢になっている恐れがあれば、まずは原因疾患を突き止めます。食事では、消化しづらい高脂肪食や刺激物の摂取、飲酒を控え、うどんや白粥、リンゴ、バナナなどの消化しやすく柔らかい食べ物を食べましょう。
また、お薬の副作用による下痢の可能性があれば、医師の判断で処方薬の変更や減薬を行います。
下痢でお悩みの方は
当院までご相談ください
 「自分は下痢になりやすい体質だ」と自己判断せず、専門医に相談しましょう。何らかの疾患が下痢の原因となっている可能性もありますし、症状の改善によって生活の質(QOL)の向上も期待できます。当院では、下痢の根本原因を特定し、辛い症状を改善できるように努めています。下痢でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
「自分は下痢になりやすい体質だ」と自己判断せず、専門医に相談しましょう。何らかの疾患が下痢の原因となっている可能性もありますし、症状の改善によって生活の質(QOL)の向上も期待できます。当院では、下痢の根本原因を特定し、辛い症状を改善できるように努めています。下痢でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。