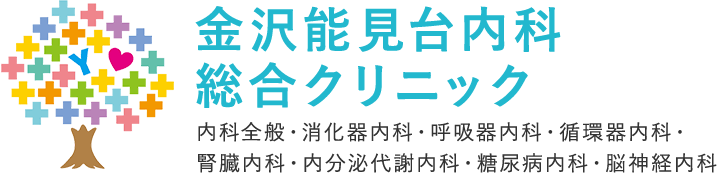脂質異常症とは
 以前は脂質が過剰な状態だけを治療が必要な高脂血症という疾患としていましたが、脂質の不足も疾患の原因になることがわかり、脂質はバランスが重要であるという認識に変わったことで、現在ではバランスが崩れた状態を脂質異常症としてとらえ、治療を行っています。血中に含まれる脂質は、細胞を作る材料であり、細胞のエネルギー源という役割を担っています。血中の脂質には、細胞へ脂質を届けるLDLコレステロール、余分な脂質を回収するHDLコレステロール、エネルギーとして消費される中性脂肪(トリグリセライド)があります。善玉・悪玉と表現されることもありますが不要な脂質はなく、どれも身体に欠かせない物質であり、バランスがとれていることが重要です。バランスが崩れると過剰になった脂質が血管壁に付着し、血管の狭窄や閉塞につながる可能性があります。
以前は脂質が過剰な状態だけを治療が必要な高脂血症という疾患としていましたが、脂質の不足も疾患の原因になることがわかり、脂質はバランスが重要であるという認識に変わったことで、現在ではバランスが崩れた状態を脂質異常症としてとらえ、治療を行っています。血中に含まれる脂質は、細胞を作る材料であり、細胞のエネルギー源という役割を担っています。血中の脂質には、細胞へ脂質を届けるLDLコレステロール、余分な脂質を回収するHDLコレステロール、エネルギーとして消費される中性脂肪(トリグリセライド)があります。善玉・悪玉と表現されることもありますが不要な脂質はなく、どれも身体に欠かせない物質であり、バランスがとれていることが重要です。バランスが崩れると過剰になった脂質が血管壁に付着し、血管の狭窄や閉塞につながる可能性があります。
脂質異常症の原因
遺伝的素因を背景に生活習慣が関与して発症・進行する原発性と、他の疾患によって発症・進行する続発性に分けられ、続発性の脂質異常症は原因疾患の治療が不可欠であり、それによって脂質のバランスも整いやすくなります。原発性の脂質異常症は生活習慣病であり、カロリーや脂肪の過剰摂取や運動不足などが発症や進行に大きく関わります。
また、女性は更年期や閉経によって女性ホルモン分泌が低下すると、脂質異常症の発症・進行リスクが上昇します。それまで問題がなかった場合も、更年期以降は健康診断の結果をしっかり確認してください。
脂質異常症と動脈硬化
他の生活習慣病と同様に、脂質異常症も動脈硬化を進行させます。過剰なコレステロールが血管の内皮細胞の下に入りこんで酸化し、白血球の1種がそれを取り込んでドロドロした塊(粥腫)になることで血管の内膜が押し上げられ、血管が狭窄するアテローム動脈硬化を起こします。進行するとプラークが血管壁にでき、プラークが破綻すると血栓となって血流を阻害し、血栓がはがれてしまうと血流で流れた先の血管を詰まらせ、脳梗塞や心筋梗塞などの深刻な疾患を発症します。動脈硬化を進行させないためには、脂質のバランスがとれた状態を維持することが不可欠です。脂質異常を指摘されたら、できるだけ早く受診して適切な治療につなげましょう。
脂質異常症の症状
脂質異常症は早期にも、進行してからも自覚症状を起こすことのない、やっかいな疾患です。健康診断の血液検査で脂質異常を指摘されたら、早めに受診して脂質異常のタイプに合わせた治療を受けてください。また、治療を受けて脂質バランスが良好になったかどうかも、検査を受けてみないとわかりません。治療を続けながら定期的に検査を受け、脂質の状態をしっかり把握することが重要です。
脂質異常症の治療
食事療法と運動療法を中心とした治療を行い、それで十分な効果を得られない場合は薬物療法を併用します。脂質異常症のタイプによって効果的な対策や治療薬が変わってきますので、定期的に検査を受けて治療効果を確かめ、状態に合わせた治療を続けましょう。
食事療法
肥満している場合には適正体重を目標にカロリー制限を行います。また、脂質異常のタイプにより、適切な食事内容が変わります。余分な脂質を回収するHDLコレステロールが不足している場合には、松の実、くるみ、ゴマなどが適していますが、過剰に摂取すると他の疾患につながる可能性もありますので適量をとるようにしてください。LDLコレステロールを下げるためには、野菜・大豆・魚介類などを中心とした日本食が適しています。また、習慣的に飲酒される方で中性脂肪が過剰な場合には、禁酒や節酒が必要になります。
運動療法
早足のウォーキングといった有酸素運動を30分、週3回以上の頻度で習慣的に行うようにします。また、筋肉を強化することで運動効果が高くなり、血行が促進されて代謝も改善します。ご自宅でできるストレッチや無理のない筋力トレーニングなどを取り入れ、身体を動かす機会をこまめに作りましょう。なお、患者様によっては運動に制限が必要な場合もありますので、適した運動について医師と相談してから行うようにしてください。
薬物療法
脂質異常症のタイプにより、処方する薬が異なります。中性脂肪を下げる薬、LDLコレステロール値を下げる薬、中性脂肪とLDLコレステロールの値を下げる薬などがあり、適切な薬を内服することで血中の脂質バランスをコントロールします。