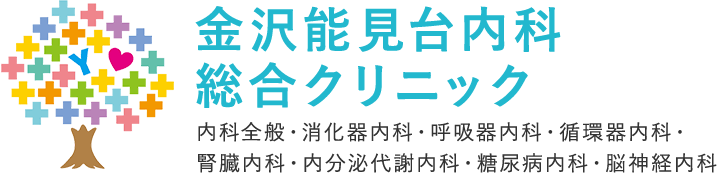心電図検査で
異常を指摘された方へ
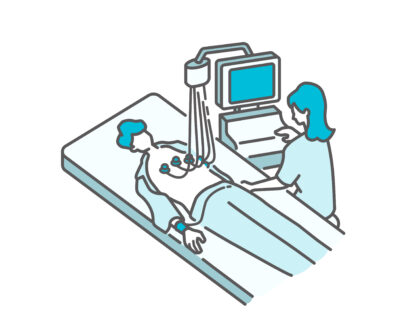 心電図検査は、心臓の電気的な活動を詳しく調べる検査方法です。心臓は、収縮と拡張によって血液を全身に送り出すポンプのような役割を担っており、この運動を拍動と言います。拍動は、一定のリズムで起こる電気信号が心臓の筋肉(心筋)へ伝達し、心臓全体を刺激させることで生じます。心電図検査は、これらの電気的な活動を写し出し、波形として記録して計測します。健康な方でも正常と異なる波形があると指摘される可能性はありますが、異常が指摘された方は、判定区分を読み、必要な精密検査を受けに行きましょう。
心電図検査は、心臓の電気的な活動を詳しく調べる検査方法です。心臓は、収縮と拡張によって血液を全身に送り出すポンプのような役割を担っており、この運動を拍動と言います。拍動は、一定のリズムで起こる電気信号が心臓の筋肉(心筋)へ伝達し、心臓全体を刺激させることで生じます。心電図検査は、これらの電気的な活動を写し出し、波形として記録して計測します。健康な方でも正常と異なる波形があると指摘される可能性はありますが、異常が指摘された方は、判定区分を読み、必要な精密検査を受けに行きましょう。
心電図検査結果の見方
| A判定 | 正常範囲内の数値であり、今後も定期的な健康診断を受けましょう。 |
|---|---|
| B判定 | 軽度異常あり。ただし、日常生活に支障はありません。 年に1度の健康診断を受け、変化がなければ問題ないと考えられます。 |
| C判定 |
異常あり。再検査または経過観察を必要とします。生活習慣を見直し、精密検査をお勧めします。 |
| D判定 | 治療が必要な所見あり。速やかに精密検査を受けましょう。 |
異常Q波
| 所見名 | 所見説明 |
|---|---|
| 心筋梗塞など (陳旧性含む) |
心筋梗塞といった心筋症の所見がある可能性がありますので、判定区分を読んでいただき、受診をご検討ください。 |
| 異常Q波 | 心筋梗塞や心筋症などの病気だけでなく、健康な方にも時折見られる所見です。受診の必要性については判定区分をご確認ください。 |
| 異常Q波(下壁) | 心筋梗塞や心筋症などの疾患だけでなく、肥満者にも異常Q波(下壁)の所見が見られることがありますので、受診の必要性は判定区分からご確認ください。 |
| q波 | 左心室肥大や心筋梗塞などの疾患だけでなく、健康な方にもよくあります。受診の必要性は判定区分からご覧ください。 |
| QS波(前壁) | 左心室肥大や心筋梗塞などの疾患だけでなく、高身長や痩せ型の健康な方にもQS波(前壁)が見られることがあります。受診の必要性は判定区分からご確認ください。 |
| q波(側壁) | 左心室肥大や心筋梗塞などの疾患だけでなく、健康な方にもq波(側壁)がよく見られますので、受診の必要性は判定区分をご確認ください。 |
| q波(下壁) | 心筋梗塞や肥満の方に多い所見です。診察の必要性については、判定区分からご確認ください。 |
| r波増高不良 |
左心室肥大の患者様をはじめ、心筋梗塞が回復された方、健康な方にもよく見られます。 診察の必要性については、判定区分からご確認ください。 |
QRS軸偏位
| 所見名 | 所見説明 |
|---|---|
| 左軸偏位 | 心臓の収縮を促す電気の流れが左側に傾いています。この所見だけでは問題になりませんが、左心室肥大などの病気と結び付くことがあります。また、肥満や高齢の方にも見られます。 |
| 左軸偏位(高度) | 心臓の収縮をサポートする電気の流れが左側へ傾いています。肥満や高齢者などにも頻繁に見られ、左心室肥大などの疾患とつながる可能性があります。ただし、この所見だけでは問題になりにくいです。 |
| 左軸偏位(軽度) | 心臓の収縮を助ける電気の流れが左側へ傾いています。肥満や高齢の方々でもよく見られ、左心室肥大などの疾患と関連していることがありますが、この所見だけで心配する必要はありません。 |
| 右軸偏位(高度) | 心臓の収縮を引き起こす電気の流れが右に偏っている状態です。主に重症肺疾患の際や、痩せ型の健康な方でも見られます。これだけで特に心配する必要はありません。 |
| 右軸偏位(軽度) | 心臓の収縮を促す電気の流れが右に傾いている状態です。主に重症肺疾患の際や、健康な細身の方(特に若い女性)でも認められます。この所見だけでは、問題とはなりません。 |
| 不定軸 | 心臓の収縮を促す電気の流れが左または右に傾いているか判断できない状態です。この所見だけでは、心配する必要はありません。 |
R波増高
| 所見名 | 所見説明 |
|---|---|
| 左室側高電位差 | 左心室肥大の可能性もありますが、健康な方(特に身長が高く痩せ型の若い男性)にも多く見られる所見です。この所見だけでは深刻な問題ではない可能性があります。 |
|
左室側高電位差 |
左心室肥大の可能性もありますが、健康な方(特に身長が高く痩せ型の若い男性)にも多く見られる所見です。この所見だけでは深刻な問題ではない可能性があります。 |
ST低下(極高度)
| 所見名 | 所見説明 |
|---|---|
| ST低下(極高度) | 狭心症や重度の心肥大などが強く疑われます。特に、胸痛などの自覚症状がある方は受診してください。 |
| ST低下(高度) | 狭心症や重度の心肥大などが強く疑われます。特に、胸痛などの自覚症状がある方は受診してください。 |
| ST低下(中等度) |
狭心症などに関連する重要な所見が見られる可能性があります。ただし、痩せ型の若い健康な女性にも多く見られます。 受診の必要性については、判定基準をご確認ください。胸痛などの自覚症状がある場合は、早めに受診することをお勧めします(特に高血圧、脂質異常、糖尿病のある中高年者の方々)。 |
|
ST低下(軽度虚血型) |
狭心症などに伴う重要な所見があるかもしれません。しかし健常な痩せ型の方々(特に若年層の女性)にも多く見られます。受診の必要性は、判定基準からご確認ください。 |
| ST低下(軽度非虚血型) | 狭心症などが疑われます。ただし、痩せ型で健康な若年層女性にも見受けられます。判定区分を読み、受診の必要性を決定してください。 |
| ST低下(軽微) | 健康な女性でも見られる所見です。しかし、心肥大や狭心症などの病気の兆候かもしれません。受診が必要かどうかは、判定区分からご確認ください。 |
|
ST低下(軽微正常) |
心肥大や狭心症がないとは限りませんが、一般的には深刻な問題ではないことがほとんどです。 |
T波異常
| 所見名 | 所見説明 |
|---|---|
| 陰性T波(中等度) | 心筋梗塞や心筋症などの状態で見られることがあるため、原因を明らかにするため、循環器専門医による詳細な検査を受けるのが望ましいです。また、健康な方々(特に若い女性)でも、この所見が現れることがあります。診察の適否については、判定基準をご覧ください。 |
|
陰性T波(軽度) |
虚血性心疾患や心筋梗塞などの要因が疑われます。しかし、健康な方々(特に女性)にも見られることがあるため、診断の必要性については、判定基準からご確認ください。 |
| 平低T波 | 心筋梗塞や左室肥大などによって引き起こされる可能性があります。ただし、健康な方にも見られることがあります。したがって、診察の必要性については、判定基準をご確認ください。 |
| その他の陰性T波 | 複数の潜在的要因が関係しております。しかし、健康な方でも見られるため、診察の必要性については、判定基準をご覧ください。 |
心房伝導障害
| 所見名 | 所見説明 |
|---|---|
| Ⅰ度房室ブロック | 心臓上部での電気の流れに、時間がかかっている状態を示しています。 |
| Ⅰ度房室ブロック(軽度) | 心房から心室への刺激伝達に軽微な問題が観察されます。健康な方(特に若い方)でも見られることがありますので、診察の必要性については判定基準をご確認ください。 めまいや失神などの症状を伴う場合は、ご相談ください。 |
| Ⅱ度(中等度)/W症候群(持続性)/WPW症候群(間欠性)/M-Ⅰ、M-Ⅱ | 心房と心室の間に通常の電気刺激伝導路とは異なる副次的な伝導路が存在しており、心室が早く興奮する状態です。診察の必要性については診断基準をご確認くだ |
| PQ短縮 | 心房から心室への刺激が通常よりも短時間で伝わり、刺激伝達路に異常が疑われます。心臓が異常に速く鼓動する可能性がありますので、発作的に動悸があった場合は、お気軽にご相談ください。 |
心室伝導障害
| 所見名 | 所見説明 |
|---|---|
| 完全右脚ブロック (持続性) |
心室内に存在する3つの刺激伝達路の中で、右側の1本に障害があり、正常に伝達されていない状態です。高血圧など様々な要因が考えられます。受診の必要性は、判定区分をご確認ください。 |
| 完全右脚ブロック (間欠性) |
心室内に存在する3つの刺激伝達路の中で、右側の1本の伝達に時々障害が発生する状態です。高血圧などの要因が考えられるため、受診の必要性は、判定区分をご確認ください。 |
| 不完全 右脚ブロック |
心室内にある刺激伝達路の異常を疑われる所見です。しかし、正常であっても時折見られ、これだけでは大した問題とは言えません。受診の必要性は、判定区分をご確認ください。 |
| V1・2のRR'型 | 波形に変化が見られますが、重大な所見ではありません。これだけで大きな問題というわけではありません。 |
不整脈
| 所見名 | 所見説明 |
|---|---|
| 上室期外収縮 (頻発) |
通常の心臓の収縮刺激以外に、心房から異常な刺激が頻繁に生じ、心拍が乱れます。通常は治療が必要ないことがほとんどですが、一部の方(中年女性や高齢者など)には特に、原因や心房細動の進行リスクを評価するため、診察をお勧めする場合があります。詳細は判定区分をご確認ください。 |
| 心室期外収縮 (頻発) |
心臓を収縮させる刺激だけでなく、心室から異常な刺激が何度も生じ、拍動が不規則に乱れます。動悸や失神を伴わない場合は、治療は必要ありませんが、状況によっては検査を受けていただく必要もあります。 |
| 移動性心房調律 (正常) |
通常、心臓の収縮刺激発生地点は一定ですが、心房内でその場所が移動する現象が見られます。この所見だけでは問題がないとされます。 |
| 心室期外収縮 (2連発) |
心臓を収縮させる通常の刺激だけでなく、心室から異常な刺激が2回続けて生じ、心拍が乱れています。この状態が繰り返されると、動悸や失神を招く可能性があるため、判定区分を確認の上、循環器科へご相談ください。 |
| 心室期外収縮 (多形性) |
通常の心臓収縮刺激に加えて、心室内の複数の場所から異常な刺激が生じ、心臓の鼓動が乱れる状態です。可能性としては重大な心臓疾患があるかもしれませんので、速やかに循環器科を受診されることをお勧めします(特に動悸や失神がある方は注意が必要です)。 |
| 心室期外収縮 (RonT) |
心臓が通常の収縮刺激だけでなく、前の心拍と重なって異常な刺激を生じさせている状態です。失神のリスクもあるため、判定区分をご確認いただき、お早めに受診してください。 |
| 心房細動 | 心房が不規則に活動し、極めて不規則な心臓の鼓動をもたらします。この症状は逆流症や心筋症、甲状腺亢進症などによって起こります。 心房内で血塊ができ、脳梗塞のリスクが高まることがあります。また、脈拍が極端に速くなったり遅くなったりすると、全身に必要な血液を届けられなくなり、動悸や息切れが生じる恐れがあります。 |
| 異所性心房調律 (ほぼ正常) |
心臓の収縮刺激が、通常の心房内以外の部位から生じている状態です。この所見だけでは特に問題はないとされます。 |
| 上室期外収縮 (2連発) |
心臓を収縮させる刺激以外に、心房から不定期な刺激が2回連続で発生し、心拍が乱れています。原因・危険な不整脈との関連について十分に検査する必要がありますので、ぜひ受診してください。 |
| 上室期外収縮 (多源性) |
心臓を収縮させる刺激に加えて、複数の箇所から異常な刺激が多発し、心拍が乱れてしまう状態です。原因に加えて、危険な不整脈との関連性について詳しく検査する必要がありますので、ご相談ください。 |
| 洞性不整脈 | 1分間に100~119回以上という若干速い心拍が確認されてます。緊張や発熱、重度の貧血、甲状腺機能亢進症などに関連している可能性がありますが、心臓疾患によって発生しているケースもあります。 |
|
QRS幅の広い |
心室頻拍や変行伝道現象、またはWPW症候群による上室頻拍など、重大な不整脈(速い心拍)が心配されます。 |
| QRS幅の狭い 頻拍 |
上室頻拍や心房粗動など、治療が必要な不整脈(速い心拍)が起こっている可能性があります。 |
| 徐脈 (高度) |
1分間に40回以下の非常に遅い心拍数です。心疾患の可能性が強く疑われますが、マラソンや水泳などの激しい長距離運動をする方、自律神経の異常、甲状腺機能低下などの患者様にも多く見られます。心拍数が少ない時に息切れやめまい、失神が起きるときは、早めに受診しましょう。 |
| 徐脈 (中等度) |
1分間に41〜45回の遅い心拍数です。マラソンや水泳などの激しい長時間の運動をする方、自律神経の異常、甲状腺機能低下などの患者様によく見られますが、心疾患も疑われます。 心拍数が低くて息切れやめまい、失神が起きる場合は、早めにご相談ください。 |
| 徐脈 (軽度) |
1分間に46〜50回の少し遅い心拍数です。マラソンや水泳などの長時間の激しい運動を行う方、自律神経の異常、甲状腺機能低下などにかかっている方に多いですが、心疾患の可能性も考えられます。受診の必要性は、判定基準をご確認ください。 |
| 上室期外収縮(散発) | 心臓の通常の収縮リズムだけでなく、心房から異常が生じた結果、不規則な拍動が生じる現象です。高血圧、心疾患、貧血などの他、緊張やストレスによって引き起こされることがあります。 |
| 心室期外収縮(散発) | 心臓を収縮させる刺激だけでなく、心室から異常な刺激が生じ、乱れた拍動が生じる状態です。心疾患の患者様だけでなく、健康な方でも緊張やストレスによって発生する場合があります。 |
その他
| 所見名 | 所見説明 |
|---|---|
| 低電位差 | 心電図全体の波の高さが基準より低い状態を指します。心臓の周りに水が溜まる心包膜効果や、肺気腫や肥満の方にも見られる現象です。 |
| ST上昇 |
放置して問題ない軽微なものから緊急の受診が必要な状況まで様々なケースがありますので、判定基準に従ってください。 若年で細身の男性でも正常な状態で見られることがあります。胸痛など自覚症状がある場合は、急性心筋梗塞の可能性もあるため、早めに循環器科を受診してください(特に中高年男性、高血圧、脂質異常、糖尿病の方は注意しましょう)。 |
| ブルガダ型 (coved) |
危険な不整脈(心室細動、心室頻拍)が発生する可能性があります。特に、過去に失神した経験がある場合、突然死した血縁者がいる場合は、放置せずに受診してください。 |
| ブルガダ型 (SB) |
危険な不整脈(心室細動、心室頻拍)が発生する可能性があります。過去に失神経験がある場合や突然死した血縁者がいる場合は、ご相談ください。 |
| ブルガダ型 の疑い |
典型的なブルガダ型心電図ではないかもしれませんが、疑いは排除できません。過去に失神経験がある場合や突然死した血縁者がいる場合は、ご相談ください。 |
| 右房負荷 | 右心房の拡大が観察されます。先天性心臓疾患や肺高血圧などの他、胸郭の変形によっても引き起こされる可能性があります。他の症状とともに総合的に判断されるため、判定基準に従って受診してください。 |
| 左房負荷 |
左心房が拡大している所見が確認されます。これは、左心室肥大や心臓弁膜症などの疾患だけでなく、身長が高い方や漏斗胸の方にも見られることがあります。他の検査結果と照らし合わせて総合的な判断を行い、判定区分に従ってください。 |
| 反時計回転 (正常) |
心臓の位置が僅かに左回り(反時計方向)に回転している状態を指します。通常、問題はありません。 |
| 時計回転 (正常) |
心臓の位置が僅かに右回り(時計方向)に回転している状態を指します。通常、問題はありません。 |
| T波増高(高度) | T波が顕著に高くなっている状態です。これは心室肥大や高カリウム血症などの患者様にも現れますが、健康な方でも時折みられます。受診が必要かどうかは、判定区分からご覧ください。 |
| T波増高(軽度) | T波が若干高くなっている状態です。心室肥大や高カリウム血症などの患者様にも現れますが、健康な方は放置しても問題ない可能性が高いです。受診が必要かどうかは、判定区分からご覧ください。 |
| 陰性U波 | 通常、上向きを示すべきU波が下向きに変わっています。これは心臓弁膜症や狭心症などに関連する可能性があります。他の所見と照らし合わせて全体を判断するため、判定基準に則ってください。 |
| QT延長 の疑い |
心室の収縮時間が通常よりもやや長くなる傾向が見られます。この症状は電解質異常や先天性心臓疾患と関連しています。過去に失神発作の経験がある場合や、突然死した血縁者がいる場合は、ご相談ください。うつ病の治療薬や抗生物質の使用によって症状が悪化することがあるため、これらの医薬品を利用する際には、主治医と相談してください。 |
心電図異常から
疑われる疾患
不整脈
完全左脚ブロックや房室ブロックは心臓の異常が疑われ、特に動悸、息切れ、胸部不快感などの症状を伴っている場合は、慎重に判断しなければなりません。また、ブルガダ症候群のように稀に突然死を引き起こす不整脈も存在します。不整脈の種類は多岐にわたります。そして、健康診断の目的は、不整脈による突然死リスクのある方を見つけ出すことにあります。
虚血性心疾患
虚血性心疾患が疑われる場合、診断の所見欄には、「心筋虚血、心筋障害、Q波、R波低下、下壁梗塞」などが示されます。過去に心筋梗塞の経歴がある可能性も考慮されるため、当てはまる患者様は注意が必要です。
同時に、以前に胸部痛を経験した方や、糖尿病、脂質異常症、喫煙歴のある方も、虚血性心疾患のリスクが上昇しやすいです。このような要因が重なると、虚血性心疾患の進行リスクも高まるので、当てはまる患者様は要注意です。
その他
左室肥大や心室肥大という単語は、主に高血圧による心筋の肥大を指します。心臓超音波検査でその程度をチェックしますが、肥大が将来的に心筋梗塞などのリスクと関連することから、高血圧の適切な治療が重要であり、将来の心疾患を予防するために欠かせません。
心電図異常を指摘された場合の
再検査(要精密検査)
 まず、心電図の検査結果を基に心電図の再検査を実施いたします。変化があった場合は、精密検査が必須となります。変化がない場合、追加の検査を行うかどうかを判断します。
まず、心電図の検査結果を基に心電図の再検査を実施いたします。変化があった場合は、精密検査が必須となります。変化がない場合、追加の検査を行うかどうかを判断します。
初回の心電図に異常や変化がある場合には、心臓エコー検査が必須です。不整脈の可能性がある場合、24時間心電図(ホルター心電図)を実施し、心臓の動きを長時間にわたって調べます。不整脈や不規則な脈拍が見られた場合は、心不全の可能性を疑います。症状の程度を確認するために、採血(BNP)も実施します。虚血性心疾患の可能性が高い場合、運動負荷試験や心臓CT検査により、冠動脈の狭窄の度合いをチェックします。
心電図検査で異常を
指摘されなかったら問題ない?
 弁膜症といった心臓事態の構造の異常、狭心症や不整脈においては、発作が起きない場合や、病気が進行しないと認められないこともあります。それゆえに、測定時の心電図が正常であっても、症状がある場合は、循環器内科へ受診されることをお勧めしているのです。
弁膜症といった心臓事態の構造の異常、狭心症や不整脈においては、発作が起きない場合や、病気が進行しないと認められないこともあります。それゆえに、測定時の心電図が正常であっても、症状がある場合は、循環器内科へ受診されることをお勧めしているのです。
一方、健診結果で「異常」と判定された波形であっても、最終的には「問題なし」や「経過観察」と決定となるケースもあります。心臓の基本的な動きが正常であり、突然死するリスクが低い場合は、治療の要否がないと推察されることもあります。
心電図異常(循環器疾患)の予防
高血圧、糖尿病、動脈硬化、肥満、心疾患などの生活習慣病を改善することは、心臓病を予防するのに有効です。疲労やストレスを取り除くことや、適度な運動をすること、十分な睡眠をとること、脂肪やコレステロールを抑え、栄養バランスの取れた食事を摂取すること、そして禁煙・節酒を心掛けましょう。