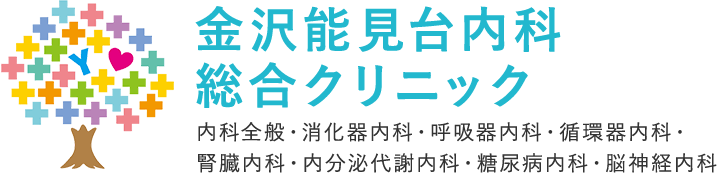おならでお悩みの方へ
 おならは、腸内に溜まった気体が肛門から排出される現象です。おならは、緊張した時や食事中に吸い込んだ空気と、腸内細菌が食物を分解する過程で発生するガスが混ざったものです。また、消化器の病気や食生活の乱れなどが原因で、おならの回数が増えることがあります。
おならは、腸内に溜まった気体が肛門から排出される現象です。おならは、緊張した時や食事中に吸い込んだ空気と、腸内細菌が食物を分解する過程で発生するガスが混ざったものです。また、消化器の病気や食生活の乱れなどが原因で、おならの回数が増えることがあります。
おならの回数が多くなる原因
食物繊維が豊富な食事
食物繊維が豊富な食事によって腸の機能が向上し、便通が改善されますが、摂取した量によってはおならの回数が増えます。なお、この場合、嫌な臭いはしません。
肉類の過剰摂取
肉類を過剰摂取すると、小腸で完全に分解・消化・吸収されず、大腸に運ばれる量が増加します。そして、ウェルシュ菌などの腸内細菌によってタンパク質が分解される際に腐敗して、アンモニア、スカトール、硫化水素、二酸化硫黄などの悪臭を放つガスが発生し、おならが臭くなる原因となります。
ストレス
緊張などのストレスが原因で空気を吸い込む量が増えます。これは呑気症という病気で、お腹の中にガスが蓄積します。
疾患
過敏性腸症候群や呑気症などによって腸内にガスが蓄積し、おならの回数が増えます。また、大腸がんが進行すると便秘になるため、結果としておならが増えます。
おならを伴う病気
呑気症
呑気症は、食事中などに無意識に大量の空気を吸い込み、しゃっくりやげっぷとして排出されなかった空気が腸内に溜まることで生じます。腸内に空気が溜まると、おならの回数が増えます。早食いや口呼吸、一気に食べたり飲んだりすることが多い、ストレスが溜まりやすい、神経質な性格の方は発症しやすいとされています。
過敏性腸症候群
過敏性腸症候群は、検査で器質的異常が発見されないのにもかかわらず、下痢や便秘、腹痛などの症状が慢性化する疾患です。疲労や気温の変化、不安や緊張などのストレスが発症に繋がるとされています。おならの悩みはなかなか人に相談しづらいこともあり、気にし過ぎてしまうことで便秘になることもあります。また、おならが周りに気づかれた経験がある方は、多くの人の前に出ることが不安になります。
大腸がん
発症初期の大腸がんは自覚症状が乏しいです。進行すると下痢や便秘、腹部膨満感、便が細くなる、下血、血便などの症状が現れます。また、腸管が狭くなりおならや便秘が起こりやすくなります。便潜血検査で陰性だった場合も、がんが直腸から遠い場所に発生している場合がありますので、定期的に大腸カメラ検査を受けて、大腸がんを早期発見できるようにしましょう。
日頃からできる予防方法
肉類は食べ過ぎないようにする
肉類を過剰に摂取すると、ウェルシュ菌などによって分解される際に腐敗し、悪臭を放つガスが発生することで、おならの臭いが強くなります。このようなことを防ぐためには、善玉菌を増やして腸内環境を改善することが重要です。善玉菌が豊富に含まれるヨーグルトなどを日頃から意識して食べることをお勧めします。
生活習慣を改善する
便秘が長引くと膨満感やおならの増加に繋がりますので、日頃から以下を意識して便秘を防ぎましょう。
- おならを我慢しない
- 便意を感じたら我慢しない
- 適度な運動を習慣化する
- 食物繊維を意識して摂取する
- 十分な水分補給をする
ご自宅で便意を感じた際は、我慢せずに排便しましょう。便秘になると腸内にガスが溜まり、より膨満感が増すという負の連鎖に繋がります。食事では、乳酸飲料や食物繊維、ヨーグルトを意識して摂取することがお勧めです。また、ウォーキングや足踏み、ヨガなどの運動を習慣化することもおすすめです。
ストレスを適度に発散する
胃腸の機能とストレスは繋がりが深いです。過敏性腸症候群は心理的要因、身体的要因、環境的要因によって起こります。ストレスが溜まりやすく、神経質な性格の方は、腹部の膨満感やおならの臭いを心配しやすいです。旅行やスポーツなどでリフレッシュできる時間を作るなど、ご自身に合ったストレス発散方法を見つけましょう。
おならの対策
専門医に相談しましょう
 おならの回数が増えたり、嫌な臭いや下痢、腹痛などがある場合は、何らかの疾患の症状としておならが生じている可能性があります。おならの悩みはなかなか人に相談しづらいこともあり、気にし過ぎてしまうと便秘になることもあります。当院では経験豊富な医師が丁寧に診療を行っておりますので、お悩みの症状があれば、お気軽に当院までご相談ください。
おならの回数が増えたり、嫌な臭いや下痢、腹痛などがある場合は、何らかの疾患の症状としておならが生じている可能性があります。おならの悩みはなかなか人に相談しづらいこともあり、気にし過ぎてしまうと便秘になることもあります。当院では経験豊富な医師が丁寧に診療を行っておりますので、お悩みの症状があれば、お気軽に当院までご相談ください。