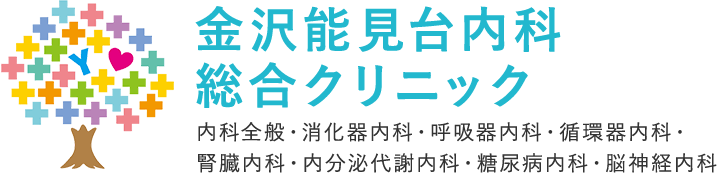頭痛について
 日本では、およそ4,000万人もの方が慢性頭痛に苦しんでいるとされています。頭痛は身近な症状として捉えられがちですが、「頭痛くらい」と軽視されがちです。しかし、重症化すれば日常生活に悪影響を及ぼすだけでなく、命に関わる病気が隠れている可能性もあります。頭痛の原因は様々であり、そのためには予防法や対処法も異なります。誤った対応をとってしまうと症状が悪化しかねないため、医療機関での診察が重要です。適切な診断や頻度、症状の重篤度評価を受け、他の原因を排除した後、予防薬などを適切に使用して治療を進めることが不可欠です。
日本では、およそ4,000万人もの方が慢性頭痛に苦しんでいるとされています。頭痛は身近な症状として捉えられがちですが、「頭痛くらい」と軽視されがちです。しかし、重症化すれば日常生活に悪影響を及ぼすだけでなく、命に関わる病気が隠れている可能性もあります。頭痛の原因は様々であり、そのためには予防法や対処法も異なります。誤った対応をとってしまうと症状が悪化しかねないため、医療機関での診察が重要です。適切な診断や頻度、症状の重篤度評価を受け、他の原因を排除した後、予防薬などを適切に使用して治療を進めることが不可欠です。
すぐに受診すべき症状
下記の症状に該当する方は、命に関わる病気が潜んでいる可能性があるため、早めに受診されることをお勧めします。
- 突然起こった、普段と異なる激しい頭痛
- ここ数ヶ月、徐々に悪化している頭痛
- 50歳以上で初めて現れる頭痛
- 意識や言葉に影響が出始めている
- 頭痛が頻繁に起こり、初めと比べて痛みが強く感じられる
- 頭痛だけでなく、めまいや吐き気、嘔吐などの症状がある
- 頭痛と一緒に、目の見えにくさや手足の動きにくさなどの異変を感じる
- 頭痛と同時に発熱や発疹が見られる
- がん疾患や免疫不全状態にいて、かつ頭痛がある
拍動性・チカチカする
「片頭痛」とは
片頭痛の原因
片頭痛の原因ははっきりとは分かっていません。しかし、悪天候や精神的なストレス、強い精神的ストレスが解消された後、過眠、睡眠不足、ホルモンバランスの乱れなどが関与していると考えられています。女性の場合、月経周期の特定の時期に片頭痛が起こるケースもあります。
片頭痛の症状チェック
以下の症状を伴う頭痛は、片頭痛の可能性が高いです。
- 頭痛がひどく「起き上がれない」「休みたい」と感じる
- 痛みが激しく生活に悪影響を及ぼしている
- 椅子に座った姿勢で前屈みになり、頭を左右に振ると痛みが増す
- 吐き気や嘔吐がある
- 光や音、匂いに対して敏感になる
- 脈打つような鋭い痛みがある
- 前兆として、視界にキラキラとした光が広がる
- 頭の片側だけが痛むわけではない
- 1回の発作が4~72時間も続く
締め付けられるような
「緊張型頭痛」とは
緊張型頭痛とは、頭や肩、首の筋肉が緊張し、ストレスなどによって引き起こされる頭痛です。緊張型頭痛は、一次性頭痛の中で最も頻繁に見られ、調査によると、日本では有病率が20%以上に達しています。この痛みは、片頭痛のように身動きが取れないほど重いものではなく、比較的何とか行動できる程度です。胃の不快感を伴っても、嘔吐することはほとんどありません。また、片頭痛と併発するケースも存在します。
えぐられるような痛み
「群発頭痛」とは
片側の目の奥が抉られたような、激しい痛みが走る頭痛です。痛みの発作は1年〜2年ごとに起こり、群発期になると、一度あたり1〜2時間もの激痛が通常1〜2カ月間続きます。早朝に痛みを感じる傾向があり、毎日同じ時間に痛みで目を覚ますケースが多いです。
生活上の注意
脳の血管が拡張するようなことは控える
群発期にお酒を摂取すると、脳の血管が拡張し、激しい痛みに苦しむ恐れがあります。発作中は絶対に飲酒をしないよう心がけましょう。逆に、飲酒後に痛みが現れない場合は、群発期から抜け出したと言えます。熱いお風呂・サウナ、辛い食事、激しい運動なども脳の血管の拡張を促しますので、群発期中は避けてください。
規則正しい生活を心がける
毎日決まった時間に起床・就寝する、十分な睡眠時間を確保する、といった自律神経のバランスを崩さないような生活を心がけましょう。また、気圧の変化にも注意が必要です。群発期中は飛行機やスキューバダイビングなど、気圧の変動が大きいアクティビティやスポーツは避けるのが望ましいです。
スマホ頭痛とは
頭痛の頻度や重症度を悪化させる原因の1つとして、スマートフォンが挙げられます。特に、頭痛のある子供や若い女性には注意が必要です。スマートフォンによる頭痛を予防する方法は下記の通りです。
スマホ頭痛の予防法
ブルーライトを削減する
仕事などで長時間スマートフォンを使用する場合は、ブルーライトをカットできるフィルムやメガネなどを活用しましょう。
また、22時以降など副交感神経が優位となる時間帯には、スマートフォンの使用を避けることが望ましいでしょう。
スマホ使用時の姿勢を改める
長時間同じ姿勢で作業することは、僧帽筋を中心とする首の後方や上背部の支持筋肉の緊張を高め、慢性的なこりや頭痛を招く恐れがあります。したがって、猫背にならないように気をつけ、作業中にも小休憩を入れましょう。
頭痛の検査
頭部CT検査
 検査台ごと体を移動し(仰向けになっていただきます)、丸い筒状の検査機器の中で、頭部にレントゲンを照射する検査です。頭部を通過したレントゲンはコンピュータ処理され、頭を輪切りにしたような断面画像が生成されます。この断面画像から頭蓋内出血や脳挫傷、脳腫瘍など、様々な病変の画像診断が可能です。頭部CT検査は時間がかからず、緊急を要する脳出血やくも膜下出血などの診断にも活用されます。
検査台ごと体を移動し(仰向けになっていただきます)、丸い筒状の検査機器の中で、頭部にレントゲンを照射する検査です。頭部を通過したレントゲンはコンピュータ処理され、頭を輪切りにしたような断面画像が生成されます。この断面画像から頭蓋内出血や脳挫傷、脳腫瘍など、様々な病変の画像診断が可能です。頭部CT検査は時間がかからず、緊急を要する脳出血やくも膜下出血などの診断にも活用されます。
頭部MRI検査
頭部MRI検査は、くも膜下出血や脳出血、脳腫瘍、髄膜炎などの病変を細かく描写できます。また、脳梗塞の早期発見に役立つため、僅かな病変でも検出可能です。頭部CT検査と同じように、丸い筒状の検査機器の中で、検査台ごと体を動かす検査です。レントゲンではなく、強力な磁石と電波を使用して断面画像を生成します。非常に強力な磁石を使用しているため、入れ歯などの金属を検査前に外さないと、正確な画像が得られなくなる恐れがあります。頭部MRI検査が必要と判断された場合には、近隣の高度医療機関へご紹介します。
髄液検査
脳と脊髄に流れる脳脊髄液を、腰椎の骨の間に針を刺して収集し、成分や色、圧力などをチェックする検査です。患者様は横たわっていただき、麻酔を施してから背中を丸めていただきます。その姿勢で脳脊髄液を採ります。この検査は髄膜炎や脳炎、くも膜下出血の診断に役立ちます。必要性がある場合には、近隣の高度医療機関に紹介いたします。
血液検査
感染症などによる頭痛の疑いがある場合に有効なのが血液検査です。白血球数や炎症反応などを調べます。また、慢性的な頭痛が続く場合には、血液検査を通して、甲状腺機能の異常がないか確かめることもあります。
よくあるご質問
後頭神経痛がある時、冷やすべきでしょうか?それとも温めるべきでしょうか?
後頭神経痛がある場合は、痛みのある箇所をアイスノンなどで冷やすことをお勧めします。一方で、温めたりマッサージを行ったりすると血管が拡張され、余計に痛みがひどくなる可能性があるのでご注意ください。
頭痛薬を飲みすぎるとどうなりますか?
月に15日以上頭痛薬を服用するのは過剰摂取になっている可能性があります。月に10日以上服用する方は、服用頻度を見直しましょう。
薬物乱用頭痛とは何ですか?
薬物乱用頭痛とは、頭痛薬の摂取頻度や量が増えることで、脳が痛みを感じやすくなり、引き起こされる頭痛のことを指します。頭痛薬の使用頻度が増えることで頭痛発作が増加し、痛みも強くなり、頭痛症状が悪化していきます。1ヵ月に10回以上頭痛薬を摂取すると、薬物乱用頭痛を引き起こす可能性があります。また、慢性的な片頭痛になるリスクは20倍にも上昇します。薬物乱用頭痛は市販の頭痛薬の乱用によく見られ、緊張型頭痛や片頭痛の患者様に多く見られます。慢性的な頭痛でお悩みの方は自己判断せず、一度受診することをお勧めします。
子供が熱を出していないのに頭が痛いと言っています。
受診した方が良いのでしょうか。
お子様の中には、大人と同じように慢性的に頭痛が生じる片頭痛や、緊張型頭痛も考えられます。さらに、思春期の子供に多い、自律神経系が関連する頭痛なども疑われます。時には、脳腫瘍や脳出血、てんかんが原因となっていることも稀に見受けられます。 お子様が頭痛を頻繁に訴えており、かつぐったりしている、食欲低下、機嫌が悪い、好きな遊びができないなどの様子を見せていた場合には、早めに受診しましょう。
性交後に頭痛を感じることがあります。
受診したほうが良いでしょうか。
激しい身体的・感情的興奮などによって、急激に血管が拡張し、脳内の神経伝達物質が変動したりすることで、頭痛を誘発していると言われています。この種の頭痛は、通常は数分~数十分で治まりますが、痛みが極めて強い・頻度が高いなどの場合は、他の疾病の有無を確認するために受診することをお勧めします