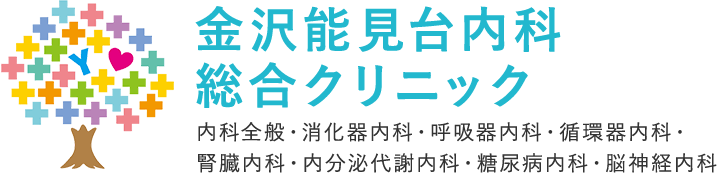心不全とは
 心不全は、心臓の機能が低下して全身に必要な血液を上手く送り出せなくなり、肺に水が溜まる状態です。心不全は疾患名ではなく、多くの心疾患が進行すると引き起こされる恐れがあります。また、その他の疾患からも発生することがあります。心臓が送り出す血液が足りなくなると、心臓は血流を維持するために多くの血液を貯め込み、左心室上流の肺血管に血液が滞留します。これにより、動作時に息切れが生じる労作性呼吸困難や、全身の血管に滞留を引き起こし、下肢の浮腫が現れることがあります。
心不全は、心臓の機能が低下して全身に必要な血液を上手く送り出せなくなり、肺に水が溜まる状態です。心不全は疾患名ではなく、多くの心疾患が進行すると引き起こされる恐れがあります。また、その他の疾患からも発生することがあります。心臓が送り出す血液が足りなくなると、心臓は血流を維持するために多くの血液を貯め込み、左心室上流の肺血管に血液が滞留します。これにより、動作時に息切れが生じる労作性呼吸困難や、全身の血管に滞留を引き起こし、下肢の浮腫が現れることがあります。
心不全の原因
心不全を引き起こす原因は大きく分けると2つあり、心臓機能に起因するものとその他の要因に分けられます。
心臓機能に原因があって生じる
心不全
心筋症
心臓の筋肉の異常により、心臓の機能が進行的に損なわれる疾患です。
心筋炎
心筋がウイルスに感染し炎症が起こり、心臓機能が低下する疾患です。近年では、コロナワクチン接種後の心筋炎が報告されています。弁の機能が低下し、血液の逆流を防げなくなることで、血液を送り出す力が衰えてしまうのです。
先天性心疾患
生まれつき心臓の形が異常な場合、心臓の機能が落ちてしまう可能性があります。
心臓以外に原因がある場合
高血圧や貧血、腎臓病、甲状腺機能亢進症(バセドウ病)、ウイルス感染症、睡眠時無呼吸症候群などに合併して心不全が起こることがあります。また、がん化学療法・放射線治療、アルコールの過剰摂取、薬物中毒、生活習慣の乱れ、肥満、加齢、喫煙、過労、ストレスなども発症の誘因となります。
心不全の症状について
主な初期症状
息切れや手足の冷え、浮腫などの自覚症状が初めに現れやすいので、これらの症状を自覚した場合は、できるだけ迅速に当院にご相談ください。
労作時呼吸困難・起坐呼吸
 全身に十分な酸素や栄養が行き届かず、例えば坂道や階段のような負担の大きい動作から息切れや疲れを感じやすくなることがあります。症状が進行すると、寝ていても同じような症状が現れ、座っていないと呼吸困難になること(起坐呼吸)もあります。また、末梢の血管まで血液が循環しなくなり、手足の冷たさなどの症状が比較的早く起こるケースもあります。
全身に十分な酸素や栄養が行き届かず、例えば坂道や階段のような負担の大きい動作から息切れや疲れを感じやすくなることがあります。症状が進行すると、寝ていても同じような症状が現れ、座っていないと呼吸困難になること(起坐呼吸)もあります。また、末梢の血管まで血液が循環しなくなり、手足の冷たさなどの症状が比較的早く起こるケースもあります。
腎機能の低下
全身への血液循環が阻害されると、腎臓に送られる血液量も減少し、尿の量が少なくなるため、体内の水分が増えて足首やすね、甲の浮腫が生じることがあります。その他に、数kgの体重増加が1週間で見られることもあります。血行障害が進展すると、腹部が膨らんだり、肺に水が溜まったりする症状が現れることがあります。
心不全進行度の検査と評価
当院では、循環器専門医や総合内科専門医が在籍し、豊富な診断経験を活かした的確な診断を行います。お気軽にご相談ください。
血液検査
心不全では、確定診断の他に合併症の検査も重要となります。
| 検査項目 | 検査目的 |
|---|---|
| BNP/ANP | 心不全の診断、治療効果の判定、予後の診断 |
| BUN/Cr | 心拍出量低下に伴う腎機能の評価 |
| AST/ALT/総ビリルビン/アルブミン(ALB) | 右心不全による肝うっ滞の評価 |
| ナトリウム(Na)/カリウム(Ca) | 電解質バランスの評価 |
| 動脈血ガス分析 | 呼吸状態の評価 |
胸部レントゲン検査
 心不全では、心拡大を伴うことが多く、心不全重症度の評価が可能です。また、体内の水分量が増える心不全では、レントゲン検査で肺うっ血や肺水腫、胸水による呼吸器障害の有無を確認できます。
心不全では、心拡大を伴うことが多く、心不全重症度の評価が可能です。また、体内の水分量が増える心不全では、レントゲン検査で肺うっ血や肺水腫、胸水による呼吸器障害の有無を確認できます。
心エコー検査
循環血液量や心室収縮力がすぐに確認できるため、診断に有効とされています。患者様の負担も少なく、ベッドに横になっていただくだけで手軽に実施できます。
心電図検査
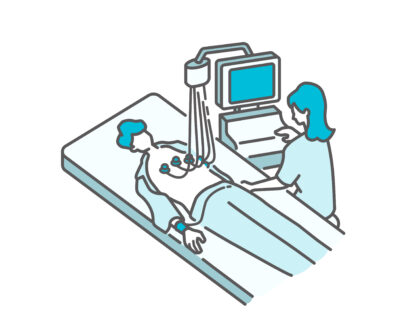 心不全による不整脈や徐脈・頻脈の評価が可能です。ベッドに横になっていただくだけで手軽に実施できます。
心不全による不整脈や徐脈・頻脈の評価が可能です。ベッドに横になっていただくだけで手軽に実施できます。
心不全の治療
心不全の治療は対症療法を目的とした薬物療法が中心で定期的な心機能の評価を行います。安静を保ち、呼吸状態が悪い方には酸素投与を行い、むくみや胸水予防のために除水を行います。
合併症状として知られる肺のうっ血の症状を良くするには、一般的に利尿薬が使用されます。これにより、不要な水分やナトリウムが体外へ排出され、浮腫みや息切れが緩和されます。再発を予防するためには、ACE阻害剤やARBなどの薬剤が使用されます。また、β遮断薬やアルドステロン拮抗薬なども使用されることがあります。薬物療法だけでは効果が不十分な場合、心不全の原因に応じて手術などの追加治療が選択されます。例えば、狭心症や心筋梗塞が原因の場合には、カテーテルやバルーンを使用して虚血を解消し、ステントを留置する処置が行われることもあります。心臓弁膜症の場合には、弁の修復や交換手術が行われる可能性があります。
日常生活の注意点
心不全の治療において、日常生活の見直しは極めて重要です。
指示通りに薬を服用する
体調が良くなったからと薬を止める方もおりますが、その結果、心不全が悪化する方も決して少なくありません。内服薬は心臓に必要なエネルギー源のようなものです。エネルギー不足にならないよう、指示通りに薬を継続することが非常に大切です。
減塩する
塩分摂取を控えることも重要です。余分な塩分は血液量を増やし、心臓に大きな負担をかけます。1日の食塩摂取量は6g未満に抑えましょう。
生活習慣の予防
毎日決まった時間に血圧や体重を測る習慣を身につけましょう。
禁煙
喫煙は心臓や血管、肺に多大な害を与え、がんのリスクを高めます。必ず禁煙しましょう。
熱いお風呂、
長時間の入浴を避ける
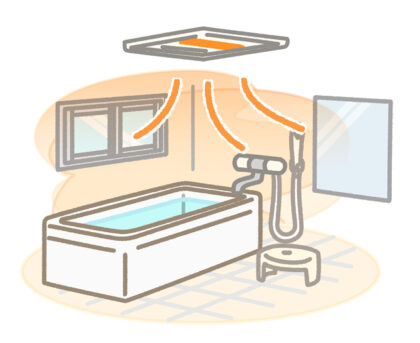 心臓への負担を減らすために、熱いお風呂や長時間の入浴は避けましょう。また、寒い季節には脱衣場を暖めてから入浴し、急激な温度変化に気をつけましょう。
心臓への負担を減らすために、熱いお風呂や長時間の入浴は避けましょう。また、寒い季節には脱衣場を暖めてから入浴し、急激な温度変化に気をつけましょう。
高齢者の心不全
高齢者の心不全の多くは、心臓が広がりにくくなる拡張機能不全によって引き起こされ、収縮力は一般的に維持される傾向にあります。拡張機能が落ちると、血液が心臓まで戻る力が低下し、うっ血を引き起こしやすくなるのです。また、高齢になると明確な症状が現れにくく、体調の変化を機に、急速に症状を進行させるケースも少なくありません。残念ながら心不全は根治が難しいです。塩分や水分の制限ができない、感染症の発症、服薬管理ができないなどにより再入院が繰り返され、QOL(生活の質)が著しく低下する可能性もあります。
ご本人だけでなく、社会的なサポートが再入院予防に非常に重要であり、多くの方が患者様をサポートすることが欠かせません。