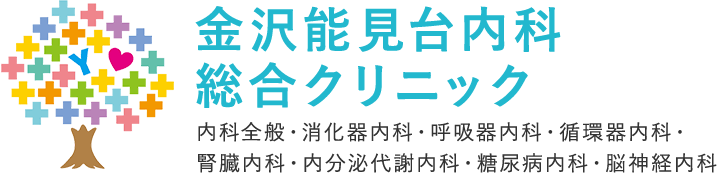血圧とは
 血液は心臓の拍動によって血管に送り出され、血管が身体の隅々まで血液を届けています。血圧は血液が血管壁を押す圧力のことで、心臓が収縮すると血液が勢いよく押し出されますので血圧が最も高くなり、静脈から戻ってきた血液を受け取る際には心臓が拡張して血圧が最も低くなります。最も高い血圧は収縮期血圧、最も低い血圧は拡張期血圧と呼ばれ、血圧計ではその両方を調べており、血圧管理には双方の記録が必要です。
血液は心臓の拍動によって血管に送り出され、血管が身体の隅々まで血液を届けています。血圧は血液が血管壁を押す圧力のことで、心臓が収縮すると血液が勢いよく押し出されますので血圧が最も高くなり、静脈から戻ってきた血液を受け取る際には心臓が拡張して血圧が最も低くなります。最も高い血圧は収縮期血圧、最も低い血圧は拡張期血圧と呼ばれ、血圧計ではその両方を調べており、血圧管理には双方の記録が必要です。
高血圧の定義
血圧は食事・動作・精神状態などによって大きく変動しますので、安静時に計測する必要があります。また、リラックスできるご自宅で計測した血圧は家庭血圧、緊張しやすい病院などで計測した血圧は診察室血圧と呼ばれており、家庭血圧よりも診察室血圧の方が高めに出やすい傾向があります。こうしたことから、高血圧の基準は家庭血圧と診察室血圧で異なります。
高血圧と定義される血圧
- 診察室血圧:収縮期血圧が140mmHg以上、または拡張期血圧が90mmHg以上
- 家庭血圧:収縮期血圧が135mmHg以上、または拡張期血圧が85mmHg以上
高血圧が続くと血管に負担がかかり続けますので、深刻な疾患の原因となる動脈硬化をはじめ、腎機能低下など多くの疾患の発症や進行を促すリスクが高くなります。適切な治療で正常な血圧を維持することが必要です。
高血圧治療ガイドライン
高血圧は血管への負担が続くことで動脈硬化を進行させ、心筋梗塞や脳卒中の発症リスクを上昇させます。さらに、影響は全身の末梢血管まで及んでしまいます。
日本高血圧学会では、適切な血圧コントロールのための目標値を下記のように設定しています。なお、日本高血圧学会『高血圧治療ガイドライン2019』では、下記以外にも様々なケースに合わせた目標の調整などについても記載があり、実際の治療では患者様の年齢や状態などにきめ細かく合わせた目標値が設定されます。
| 診察室血圧 | 家庭血圧 | |
|
・75歳未満の成人
・脳血管障害がある
・冠動脈疾患がある
・慢性腎臓病(CKD)がある(タンパク尿陽性)
・糖尿病がある
・抗血栓薬を服用している
|
130/80mmHg未満 | 125/75mmHg未満 |
|
・75歳以上の高齢者
・脳血管障害がある
・慢性腎臓病(CKD)がある(タンパク尿陰性)
|
140/90mmHg未満 | 135/85mmHg未満 |
高血圧で考えられるリスク
血圧150・160・170・180・200越えの場合
血圧150以上
軽度の高血圧ですが、動脈硬化の進行が生じやすい状態であり、血圧の影響を受けやすい心臓や腎臓にも負担がかかることで疾患発症リスクが上がります。できるだけ早く受診し、効果的でストレスの少ない生活習慣の改善方法を相談することが重要です。
血圧160以上
中程度の高血圧であり、動脈硬化進行による心筋梗塞や脳卒中のリスクが大幅に上がります。毛細血管も障害されやすくなり、慢性の腎臓病や目の血管障害による眼科疾患の発症リスクも上昇します。
血圧170以上
高度な高血圧であり、深刻な影響が心臓や脳、腎臓に及びます。心筋梗塞や脳卒中を発症するリスクがとても高く、危険な状態ですので、速やかに受診して適切な治療を受ける必要があります。
血圧180以上
重度の高血圧であり、心臓や血管、脳への障害が急激に進行するリスクがあります。心筋梗塞や脳卒中を起こすリスクがさらに上昇している状態であり、一刻も早く受診して適切な治療が必要です。
血圧200超えは危険?
緊急性が高く、即座に医療機関を受診しないと命に関わる心筋梗塞、脳卒中、腎不全などを起こす可能性が高い状態です。
高血圧の原因
高血圧は、遺伝的素因に生活習慣が関与して発症する原因疾患のない本態性高血圧と、原発性アルドステロン症や腎血管性高血圧をはじめとする原因疾患がある二次性高血圧に分けられます。日本では原因疾患のない本態性高血圧が9割を占めていますが、二次性高血圧の場合は原因疾患の適切な治療を行わなければ血圧が下がりにくい傾向があります。疑わしい場合には適切な検査を行うことが重要です。
高血圧の治療
二次性高血圧の場合は原因疾患の適切な治療が不可欠です。本態性高血圧の場合には、食事療法と運動療法を基本とした血圧コントロールを中心に行います。生活習慣の改善は続かなければ意味がありませんので、できるだけストレスのない方法を医師と相談しながら見つけることが重要です。
生活習慣の改善
塩分制限
醤油・味噌・漬物など伝統的な食品に加え、近年になって塩分の多いハムやソーセージといった加工肉やインスタント食品を食べる機会が増えたことで、もともと多かった日本人の塩分摂取量はさらに増加しやすくなっています。
1日の塩分摂取量は6g未満とされていますが、インスタント食品などには1食で1日の塩分摂取量を超えてしまうものもあります。加工食品には成分表示があり、食塩相当量が記載されていますので必ずチェックし、減塩のものを選ぶ、塩分量に合わせて使用量を決めるなどの対策をしましょう。また、調味料も使い過ぎないよう気を付けてください。
1日6g未満の塩分摂取は実際に行ってみると味が薄いと感じますが、出汁の旨味を濃くする、ハーブやスパイス、酸味などを効かせることで舌が慣れ、食の楽しみを損なわずに減塩できます。
ダイエット・肥満予防
肥満している場合には、減量して適正体重を維持することが血圧コントロールに役立ちます。適正体重であれば、他の生活習慣病をはじめ、様々な疾患の発症や進行のリスクが下がります。適正体重は、身長に対して最も疾患リスクを低減できる体重です。肥満だけでなく、低体重も疾患リスクが高くなりますので、注意が必要です。
適正体重を求めるには、まず体格指数(BMI)を算出します。
BMI=体重(kg)÷{身長(m)×身長(m)}
- 適正体重 BMI 22.0
- 低体重 BMI 18.5未満
- 普通体重 BMI 18.5以上25.0未満
- 肥満 BMI 25.0以上
肥満解消には、カロリー制限や習慣的な運動が有効ですが、過度なダイエットを行ってしまうと貧血や骨粗鬆症、生理不順などを起こしやすく、短期間に体重を減らせてもリバウンドしやすい傾向があります。徐々に体重を減らしていき、適正体重になったら、それを維持していきましょう。
減酒・禁酒
男性の1日あたりの適切な飲酒量は純アルコールで20gとされており、ビールは500mL、日本酒は1合、ワインはグラス2 杯 、ウイスキーはダブル1杯が、それぞれ純アルコール20gの目安です。なお、女性はアルコール分解速度が遅いことから、その半分程度が適量とされています。
運動
適度な運動を習慣付けることは減量にも役立ちますが、血流を促進して代謝を上げ、血管の状態を改善するためにも役立ちます。激しい運動は必要ありませんが、筋肉量が増えれば高い効果を期待できます。軽く汗ばむ程度の有酸素運動(早足のウォーキングなど)を基本に、効果的な筋力トレーニングを無理のない程度で取り入れるようにしてください。また、運動の前には必ずストレッチを行いましょう。
なお、身体の状態によっては、運動に制限が生じることもありますので、運動療法をはじめる前に必ず医師と相談してください。
禁煙
ニコチンには血管を収縮させる効果があり、高血圧の原因になります。喫煙を続けていると、厳格な食事療法や運動療法を行っても効果を得にくくなります。喫煙は高血圧以外の多くの疾患の発症や進行の原因にもなりますので、禁煙しましょう。