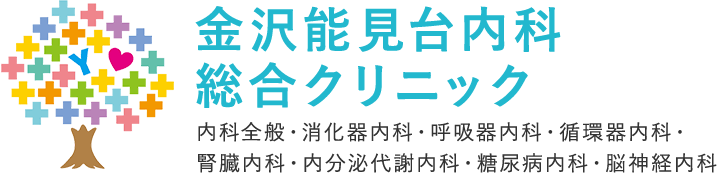甲状腺機能亢進症とは
 甲状腺ホルモンは、体の成長や代謝を調節する重要な働きを担っています。通常は下垂体から分泌される甲状腺刺激ホルモン(TSH)によって、バランスが保たれています。しかし、何かしらのきっかけで甲状腺ホルモンが過剰に分泌されると、体の成長や代謝が乱れ、ほてりや発汗、手指の震えなどの症状が現れることがあります。甲状腺異常など自己免疫が主な原因で、バセドウ病が代表的ですが、甲状腺炎や甲状腺の腫瘍などで機能が亢進するケースもあります。
甲状腺ホルモンは、体の成長や代謝を調節する重要な働きを担っています。通常は下垂体から分泌される甲状腺刺激ホルモン(TSH)によって、バランスが保たれています。しかし、何かしらのきっかけで甲状腺ホルモンが過剰に分泌されると、体の成長や代謝が乱れ、ほてりや発汗、手指の震えなどの症状が現れることがあります。甲状腺異常など自己免疫が主な原因で、バセドウ病が代表的ですが、甲状腺炎や甲状腺の腫瘍などで機能が亢進するケースもあります。
バセドウ病とは
バセドウ病は甲状腺ホルモンの分泌に必要な組織を刺激させる抗体が作られることで、甲状腺ホルモンが過剰に分泌されてしまう自己免疫疾患です。動悸や手指の震え、体重減少、突出した眼球などが一般的な症状で、喉仏の下が膨らんでいる所見が見られます。主に女性に見られ、20〜30歳の若い世代に多いです。この病気の名前は、初めて発表されたドイツの医師に因んでいます。
バセドウ病の症状
バセドウ病の主な症状は頻脈、眼球の突出、そして甲状腺の腫れです。他にも、動悸、手の震え、多量の汗、息切れ、全身の疲労感、体重の減少などが現れることもあります。ただし、このような症状は自律神経失調症や更年期障害などの疾患でも起こり得るため、正確な鑑別が重要となります。バセドウ病は無視すると、全身の様々な臓器に障害を引き起こし、重大な状態である甲状腺クリーゼに至る危険性がある病気です。
当院では、治療経験豊富な内分泌代謝・糖尿病内科領域暫定指導医が在籍しております。気になる症状がある方はお気軽に当院までご相談ください。
| 症状の種類 | 具体的例 |
|---|---|
| 全身症状 |
|
| 首の状態、表情について |
|
| 循環器症状 |
|
| 消化器症状 |
|
| 皮膚症状 |
|
| 筋骨格系の症状 |
|
| 神経・精神症状 |
|
| 月経に関する異常 |
|
バセドウ病の原因
甲状腺ホルモンは、甲状腺刺激ホルモン(TSH)が、TSH受容体と結合することで生成されます。しかし、何らかの理由でTSH受容体抗体が形成されると、TSH受容体が攻撃され続けて甲状腺ホルモンの過剰分泌が引き起こされます。それがバセドウ病の原因となります。
バセドウ病に伴う病気
眼球突出
外眼筋(眼球を囲む筋肉)や眼窩の脂肪組織の炎症・肥大化が生じることで、眼球が押し出されるようにして、眼球が突出するケースが多くみられます。
時には角膜潰瘍や結膜の腫れもみられる場合があります。
眼瞼後退
眼瞼の筋肉が緊張し、まぶたが後退することがあります。特に上瞼の筋肉が緊張すると、まぶたが下がらなくなることもあります。ホルモンバランスが正常に戻ると、通常の状態に戻ります。
複視
眼球運動のための筋肉に炎症が起こり、腫脹すると左右の眼球がスムーズに連動して動かなくなります。その結果、両眼で物を見た際、物が二重に映ることがあります。この場合、片方の目で見た時には問題なく見えます。
心疾患
甲状腺ホルモンの過剰分泌により心機能が亢進し、不整脈や頻脈が生じます。進行すると心不全をきたす恐れがあるため、日常的にホルモン値をコントロールすることが重要です。
甲状腺クリーゼ
甲状腺機能亢進症の患者様が適切な治療を受けずに、外科手術を受けたり、重度の感染症にかかったりすると、肉体に強い負担がかかるため、意識障害や全身の様々な臓器障害を引き起こすリスクが高くなります。これを甲状腺クリーゼと呼びます。
甲状腺機能亢進症の症状を少しでも自覚した場合は、早めの適切な治療によってホルモン値をコントロールしましょう。
周期性四肢麻痺
甲状腺ホルモンが亢進したまま、激しい運動を行ったり暴飲暴食したりすると、四肢麻痺が生じる恐れがあります。麻痺は一時的なものであり、基本的には数時間のうちに解消されます。ただし、麻痺を繰り返す可能性もあり、このようなケースは若い男性の患者様に多いとされています。再発を避けるためにも、ホルモン値の管理が不可欠です。
高血糖
甲状腺ホルモンはエネルギー代謝を制御するホルモンです。このホルモンが過剰になると、糖代謝異常になり、高血糖状態を招くことがあります。
骨粗鬆症
甲状腺ホルモンが亢進すると、骨の代謝が加速することがあります。骨の代謝サイクルが早くなると、骨密度が低下しやすくなり、骨粗鬆症を招きやすくなります。高齢者や閉経期の女性は特に骨粗鬆症のリスクが高いため、注意が必要です。甲状腺ホルモン値が正常になると、骨密度も改善されます。
その他
爪がギザギザになったりスプーン状に変形したりします。皮膚の白斑や、前脛骨粘液水腫(ぜんけいこつねんえきすいしゅ:脛部分に黒い色素が溜まる)などの症状を伴うことがあります。
バセドウ病の検査と診断
 バセドウ病の検査では、血液検査で甲状腺ホルモンと甲状腺刺激ホルモン(TSH)の血中濃度を測定します。
バセドウ病の検査では、血液検査で甲状腺ホルモンと甲状腺刺激ホルモン(TSH)の血中濃度を測定します。
検査の結果、FT3、FT4の甲状腺ホルモン値が高い、もしくはTSH値が低いと判明したら、バセドウ病の可能性が高いとされます。
加えて、血液検査によってバセドウ病特有の自己抗体であるTSH受容体抗体(TRAb)が陽性と分かった場合は、バセドウ病の確定診断がつきます。
バセドウ病の治療
患者様の状態に応じて、抗甲状腺薬、放射線治療、外科手術の3つの中から選択されます。
基本的には、抗甲状腺薬による薬物療法を行います。ホルモン値のコントロールができたら少しずつ減薬していきますが、再発を防ぐために一定期間服薬を続ける必要があります。ただし、抗甲状腺薬には多くの副作用があり、特に顆粒球減少症による抵抗性低下には気を付ける必要があります。また、効果が不十分であったり、治療期間が制限されたりしている場合、強い副作用が現れた場合などには、放射線によるアイソトープ療法や外科手術を選択します。
また、強いストレスや喫煙はバセドウ病を悪化させる要因になるため、生活習慣の見直しも重要な治療といえます。
薬物療法
抗甲状腺薬
20世紀中盤頃から、プロパジールやチウラジールなどが使用されています。ごく稀に顆粒球減少や無顆粒球症など、生死に関わる副作用も含まれていますので、投与を始めてからしばらくは、2週間ごとに通院し、副作用を確認する必要があります。
また、服用中に38℃以上の高熱が出たり、喉が腫れたりするなどの症状が現れた場合には、直ちに服用を中止して受診してください。
バセドウ病を
放置するとどうなる?
甲状腺機能が亢進しているのに気付かないまま放置したり、治療を止めたりすると、ほとんどの割合でバセドウ病が悪化していきます。適切な治療が重要ですので、治療を放置したり中断したりすることは避けましょう。悪化すれば治療期間が長くなり甲状腺クリーゼを起こす恐れもあります。最悪の場合、多臓器不全により突然死に至ることもあるため、医師の指示に従い、適切な治療を続けましょう。
バセドウ病と遺伝
バセドウ病は、遺伝的因子とストレス、生活習慣などの環境的要因が組み合わさり、発病する疾患です。遺伝的な影響が大きく、家族や親戚に発症者がいる場合、発病リスクが高まることが報告されています。親に病気がある場合、その子も約6~10倍のリスクで発症する可能性があるとされています。