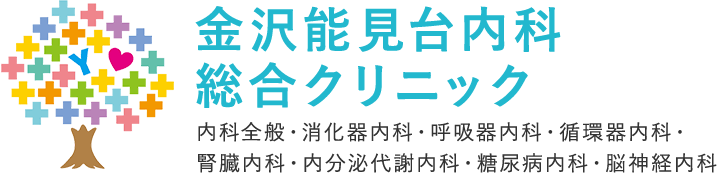甲状腺機能低下症とは
 甲状腺機能低下症とは、甲状腺の働きが低下することで、甲状腺ホルモンの分泌が不足してしまう状態です。
甲状腺機能低下症とは、甲状腺の働きが低下することで、甲状腺ホルモンの分泌が不足してしまう状態です。
甲状腺ホルモンが不足すると、疲れやすくなったり、気力が低下したり、動きが鈍くなったりするといった症状が現れます。また、むくみや冷え性、寒がり、便秘、記憶力低下といった症状も現れますが、程度が軽い場合は症状が現れにくいことがあります。
橋本病とは
甲状腺機能低下症の代表的な疾患の一つに「橋本病」があります。橋本病は、「抗サイクログロブリン抗体(TgAb)」や「抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(TPOAb)」という自己免疫抗体が、何かしらのきっかけで生成され、甲状腺の組織を攻撃し、慢性的な炎症を起こすことで、甲状腺ホルモン分泌の低下を引き起こします。ただし、これらの自己免疫抗体が形成される原因は未だに分かっていません。
また、橋本病にかかっても、甲状腺機能の低下が伴わないケースもあります。そして、症状が現れるのは特に女性に多いとされています。
橋本病の症状
| 症状の種類 | 具体的例 |
|---|---|
| 全身症状 |
|
| 体温の変化 |
|
| 首の状態、表情について |
|
| 神経・精神症状 |
|
| 循環器症状 |
|
| 消化器症状 |
|
| 皮膚症状 |
|
| 筋骨格系の症状 |
|
| 月経に関する異常 |
|
| 血液検査の異常 |
|
橋本病で顔つきが変わった?
甲状腺ホルモンの不足によって、症状が進行すると外見上にも変化が現れることがあります。特に、顔のむくみが目立ち、瞼や顔の皮膚、唇などが全体的に腫れて浮腫んだような表情になります。
橋本病に伴う病気
無痛性甲状腺炎
甲状腺の細胞が壊され、蓄積された甲状腺ホルモンが一時的に血中に放出されるため、甲状腺機能亢進症の症状が現れます。この状態は一過性であり、溜まったホルモンが全て消費されるまでの間に自然治癒します。通常、1~4か月ほどで回復します。
橋本病の急性増悪
稀に、甲状腺の腫れが急速に進行し、痛みや発熱を伴うことがあります。この場合、一時的に甲状腺内のホルモンが血中に放出され、動悸をはじめとする甲状腺機能亢進症の症状が現れることがあります。
悪性リンパ腫
甲状腺の炎症が長期間続くと、リンパ球が蓄積し、悪性リンパ腫に進展する恐れがあります。ただし、橋本病による悪性リンパ腫の発症は極めて稀です。
橋本病の検査と診断
 血液検査では、「甲状腺ホルモン(FT3、FT4)」と「甲状腺刺激ホルモン(TSH)」のレベルを測定します。FT3、FT4が低く、TSHが高い場合、橋本病を発症している可能性が高いです。また、甲状腺の自己抗体である抗サイクログロブリン抗体(TgAb)と抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(TPOAb)の検査も行い、いずれかが陽性なら橋本病と診断されます。
血液検査では、「甲状腺ホルモン(FT3、FT4)」と「甲状腺刺激ホルモン(TSH)」のレベルを測定します。FT3、FT4が低く、TSHが高い場合、橋本病を発症している可能性が高いです。また、甲状腺の自己抗体である抗サイクログロブリン抗体(TgAb)と抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(TPOAb)の検査も行い、いずれかが陽性なら橋本病と診断されます。
さらに触診を行い、橋本病でないと見られない甲状腺の凹凸した腫れが確認できるかどうかを確かめます。
橋本病の治療
橋本病でも、甲状腺機能の低下がみられない場合の治療は不要です。治療の必要性は、甲状腺機能を測定する血液検査の結果によって判断されます。
治療が必要とされた場合は、初めに薬物療法が選択されます。薬物療法は、主に甲状腺ホルモンを服薬で補うために行われます。また、甲状腺機能は、ストレスや他の自律神経系の乱れに密接に関係しています。そのため、日常生活でストレスを上手に発散できるような工夫をすることも重要です。
薬物療法(チラーヂンS)
甲状腺ホルモンのFT4と同様の機能を持っているレボチロキシンナトリウムを成分とするお薬となります。含有量の異なる薬が複数開発されているため、適量の薬から処方を始めつつ、患者様の状況に合わせて処方量を調整していきます。
1日1回、起床時または食後30分以上経過した就寝前などに服用するのが望ましいとされています。しかし、毎日一定の時間に服用することが何よりも重要ですので、患者様が飲み忘れなく継続できるタイミングに合わせることも可能です。規則正しい服薬習慣を身につけるために、お気軽にご相談ください。
同時に服用する薬に
注意してください
副作用が少ない安全な薬ですが、特定の薬やサプリメントと同時に服用すると、吸収が阻害されて効果が低下する恐れがあります。
特に鉄剤などの貧血治療薬、アルミニウムや亜鉛などの金属成分を含む薬やサプリメントとの同時服用は、チラーヂンSの吸収率を減少させることが明らかになっておりますので、ご注意ください。
また、お茶やコーヒーではなく、水や白湯での服用を推奨しております。
橋本病と遺伝
 現在も橋本病の正確な原因は解明されておりません。しかし、発症の要因として、遺伝的、環境的、内因的な要素が複雑に関わっているといわれています。
現在も橋本病の正確な原因は解明されておりません。しかし、発症の要因として、遺伝的、環境的、内因的な要素が複雑に関わっているといわれています。
遺伝的な要因は自己免疫反応と関係があり、環境要因としてはウイルス感染や薬剤などが挙げられ、さらに女性ホルモンの作用や出産などの内因的要素と組み合わさり発病する可能性があるとされております。ただし、家族歴があるからといって、必ずしも橋本病を発症するわけではありませんが、冷えや疲れやすさ、むくみ、皮膚の乾燥、顔つきの変化などの甲状腺異常の症状が生じた場合や、妊娠が判明した際には、早めに検査を受けるようにしましょう。