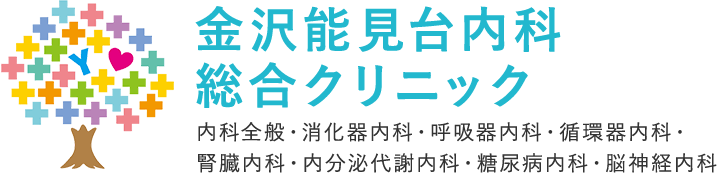心筋梗塞とは
 心筋梗塞は、心臓へ酸素と栄養を送り届ける冠動脈(または冠状動脈)が閉塞して血液の流れが滞り、心筋(心臓を動かす筋肉)が壊死する深刻な病気です。
心筋梗塞は、心臓へ酸素と栄養を送り届ける冠動脈(または冠状動脈)が閉塞して血液の流れが滞り、心筋(心臓を動かす筋肉)が壊死する深刻な病気です。
冠動脈は、大動脈弁の真上の外側で大動脈から分かれ、心臓上部を木の枝のように通り抜けています。冠動脈には右冠動脈、左前下行枝、左回旋枝の3つがあり、左前下行枝と左回旋枝をまとめて左冠動脈と呼びます。その基部を主幹部としています。
心筋が適切に動き続けるためには、これらの3本の冠動脈を通じて酸素と栄養を受け取らなければなりません。冠動脈が閉塞すると、閉塞された部分の先にある心筋は、酸素と栄養を供給されず、壊死します。壊死した心筋は元の状態に回復できません。心筋が壊死すると、心臓は全身に必要な血液を届けられなくなり、速やかに治療を行わないと生命の危険が高まります。これら3本の冠動脈の内1本が閉塞した状況を「1枝病変」、2本が閉塞した状況を「2枝病変」、3本が閉塞した状況を「3枝病変」と言います。閉塞した箇所が多いほど重症と見なされます。
急性心筋梗塞とは
心筋梗塞の大部分は、不意に発症する急性心筋梗塞です。急性心筋梗塞は、突如として血栓ができ、冠動脈に詰まりが生じることで発症します。気付かぬうちに血管が閉塞する心筋梗塞も存在しますが、ここでは急性心筋梗塞が主要な内容となります。
狭心症と心筋梗塞の違い
虚血性心疾患の1種として、狭心症が挙げられます。心筋梗塞と狭心症との違いは、冠動脈の閉塞の程度にあります。心筋梗塞では、冠動脈が完全に閉じて血流が停止するのに対し、狭心症では冠動脈の内径が狭まっているものの、やや血流が維持されている状態です。そのため、心筋梗塞の方がより危険で深刻な状態と言えるのです。両方とも、胸の痛みや圧迫感などの症状が現れますが、狭心症はこれらの症状が数分から15分程度起こるのを特徴とします。
一方で、心筋梗塞の場合は30分以上持続し、安静を保っていても、救急薬であるニトログリセリンを服用しても改善されません。また、脂汗や冷や汗、顔面蒼白感など、深刻な症状が現れます。場合によっては、嘔吐や失神など多岐にわたる症状が現れることもあります。
心筋梗塞の原因
 心筋梗塞の主な原因は動脈硬化です。動脈硬化は、高血圧や脂肪の過剰摂取などにより、血管のしなやかさが失われ、硬くなる状態です。動脈硬化が悪化すると、動脈壁が肥厚し、血管の内径が狭くなります。この血の流れが滞った状態を狭心症と呼びます。心筋梗塞のほとんどは、動脈硬化によって血管壁の内側に脂肪のコブが生じることによって引き起こされます。
心筋梗塞の主な原因は動脈硬化です。動脈硬化は、高血圧や脂肪の過剰摂取などにより、血管のしなやかさが失われ、硬くなる状態です。動脈硬化が悪化すると、動脈壁が肥厚し、血管の内径が狭くなります。この血の流れが滞った状態を狭心症と呼びます。心筋梗塞のほとんどは、動脈硬化によって血管壁の内側に脂肪のコブが生じることによって引き起こされます。
最初に、血液中のLDLコレステロール(悪玉コレステロール)が過剰に増えると、損傷した内皮細胞(動脈血管壁の最も内側にある細胞)の隙間からLDLコレステロールが血管壁の内側に入り込みます。それにより、コレステロールを追い出そうとする免疫細胞なども侵入し、血管壁がコブのように隆起します。この脂肪のコブをアテローム(粥腫・じゅくしゅ)と呼びます。肥大して破裂すると急速に血栓が作られ、血管を塞ぎます。この状態を心筋梗塞と称します。
心筋梗塞になりやすい人
心筋梗塞のリスク因子は以下のようになっています。これらの原因が3つ以上該当しており、かつ男性の場合は50歳以上、女性は60歳以上ですと、心筋梗塞のリスクが高くなります。
肥満
見た目で肥満と分かっている方だけでなく、見た目は痩せていても内臓周囲に脂肪が蓄積されている内臓脂肪型肥満(メタボリック症候群)の方も例外ではありません。その場合でも、心筋梗塞のリスクが高まります。
ストレス
精神的なストレスや、激しい労働による身体的ストレスも影響します。
喫煙
喫煙により血管が傷つき、収縮し、血液が凝固した結果、動脈硬化が起こることがあります。
家族歴
狭心症や心筋梗塞を発症した血縁者がいる場合、個人の体質や生活習慣により発症リスクがあるとされます。
心筋梗塞の引き金
以下のような生活習慣・要素は、心筋梗塞を誘発させる要因になります。
- 重労働などによる過労
- 睡眠が不足している
- 大きな精神的・肉体的ストレスがかかっている
- 食べすぎ・飲みすぎ
- うつ状態
- 急な気温の変動
心筋梗塞の症状
 心筋梗塞の典型的な症状は、脂汗をかくほどの激しい胸痛です。実際には痛みより、胸が圧迫されるような感覚や、胸が焼けるような感覚を強く経験した方もいらっしゃいます。心筋梗塞は狭心症と異なり、症状が30分以上持続するのが特徴です(狭心症の場合は数分から15分程度)。そのため、恐怖感や切迫感を感じる方がほとんどです。痛みは主に、胸の中央から全体へ広がりますが、左胸から顎の辺り、左肩から左腕にかけて広がる場合があります。また、背中、みぞおち、腕、首、歯、喉などにも痛みが現れることがあります。そのほか、伴う症状として、冷や汗、吐き気、呼吸困難、顔面蒼白、脱力感、動悸、めまい、失神、ショックなどの症状が現れることもあります。
心筋梗塞の典型的な症状は、脂汗をかくほどの激しい胸痛です。実際には痛みより、胸が圧迫されるような感覚や、胸が焼けるような感覚を強く経験した方もいらっしゃいます。心筋梗塞は狭心症と異なり、症状が30分以上持続するのが特徴です(狭心症の場合は数分から15分程度)。そのため、恐怖感や切迫感を感じる方がほとんどです。痛みは主に、胸の中央から全体へ広がりますが、左胸から顎の辺り、左肩から左腕にかけて広がる場合があります。また、背中、みぞおち、腕、首、歯、喉などにも痛みが現れることがあります。そのほか、伴う症状として、冷や汗、吐き気、呼吸困難、顔面蒼白、脱力感、動悸、めまい、失神、ショックなどの症状が現れることもあります。
心筋梗塞の検査
心筋梗塞の検査には、心電図検査、血液検査、画像検査の3つの方法があります。
血液検査
血液検査で心筋梗塞の診断が可能です。心筋梗塞が起こって心筋細胞が壊死すると、様々な酵素が血液中へ流れてしまいます。
クレアチンホスホキナーゼ(CPK)
一般的な心臓マーカーです。心筋梗塞の約4〜5時間後に、その濃度が上昇します。
CK-MB
この酵素の血中濃度が高く出た場合、心筋障害の可能性も高いです。この数値は壊死の度合いを正確に表します。
トロポニン
最近ではマーカーとして認識されるようになりました。この酵素は早い段階で上昇し、心筋梗塞を正確に診断する精度が90〜95%もあります。心筋梗塞の重症度によりますが、この酵素の血中レベルは発症後3〜12時間で上昇し始め、数日間高い値を維持します。
BNP
(脳性ナトリウム利尿ペプチド)
このホルモンの血中濃度を調べることにより、心不全(心筋梗塞などに伴う心機能低下)があるかどうかが分かります。BNPは心筋保護のために心室から分泌されるホルモンです。そのため、心臓への負荷が大きくなったり心筋が肥大したりすると、血中濃度が上昇します。自覚症状が現れる前に濃度が高くなるため、心機能障害を早期に見つけ出すのに期待できます。
心電図検査
検査を受ける方の胸部などに電極を貼り付け、心臓の電気的活動をグラフにする検査です。心筋梗塞を発症すると、一般的な波形の変化が見られるため、血管の閉塞場所や重症度を推測できます。
画像検査
胸部レントゲン検査
心臓の画像を撮影するためにレントゲンを使った検査です。心筋梗塞によって心不全を引き起こした場合、肺うっ血や心拡大が観察されます。
心エコー検査
心筋マーカーの変化や心電図よりも、心筋への血液供給不足からくる心室収縮力の低下や消失がすぐに確認できるため、診断に有効とされています。患者様の負担も少なく、ベッドに横になっていただくだけで手軽に実施できます。
心筋シンチグラム検査
(心臓核医学検査)
体内に投与した放射性同位体を使い、血流を測定するコンピュータ断層撮影です。放射性同位体元素の中には、心筋梗塞箇所に蓄積する性質を持つものがあり、これを応用して正確な診断を下します。放射線用の遮蔽装置が必要なため、緊急時には適していません。心筋梗塞の深刻度や存続している心筋の判定に用いられ、高度な医療施設で実施されます。
冠動脈造影検査
緊急病院で診断がついた際には、迅速にカテーテル検査室で検査を実施します。手首や肘、鼠径部から局所麻酔を施し、細いチューブを挿入して冠動脈造影を行います。閉塞している箇所にワイヤー線を通し、血栓吸引やバルーン拡張、ステント留置を行い、血流の再開通を促します。発症から再開通までのスピードが早いほど、壊死していない心筋が助かります。
心筋梗塞の治療
カテーテル治療
冠動脈にカテーテルを挿入し、バルーンで閉塞した箇所を拡張し、ステントで動脈を開いた状態に保つ治療法です。この治療は再灌流療法と呼ばれており、発症から12時間以内に血流を回復させるのが目的です。治療前後に激しい痛みがある場合は、モルヒネを使用して痛みを和らげることがあります。必要と判断された場合には近隣の高度医療機関へ紹介いたします。
バイパス手術
もし閉塞部位が複雑でカテーテル治療が困難とされている場合や、心筋梗塞に伴う合併症として新たな破裂が起きた場合には、脚や腕から取り出した血管を使用し、冠動脈に迂回するバイパス手術が検討されます。必要と判断された場合には、近隣の高度医療機関へ紹介いたします。
心臓リハビリテーション
心筋梗塞治療後のリハビリには病期に合わせて異なるメニューを実施します。入院中の急性期の治療に加えて、心負荷をゆっくり増やしていくリハビリを急性期リハビリと呼びます。その後の2~3ヶ月は回復期リハビリと呼ばれ、目標は退院して社会復帰することです。心臓機能テストや積極的な運動療法などが行われます。発症後の2~3ヶ月以降の期間は維持期リハビリと呼ばれます。