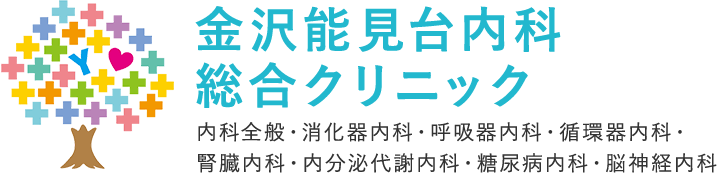息切れについて
 息切れは、身体が酸素不足を感じた時に出す信号であり、例えばランニングなどの運動をした時のような、全身の筋肉が多くの酸素を必要としている時に起こる現象です。さらに、病気の症状として息切れが発生することがあり、その場合には平地を歩くだけでも、または日常的な動き(着替えなど)でも息切れが生じる可能性があります。また、呼吸回数が増える、無意識に深呼吸する、息切れ、就寝中に呼吸が苦しくなって目を覚ます、呼吸困難など、息切れの症状は様々な形で現れることがあります。
息切れは、身体が酸素不足を感じた時に出す信号であり、例えばランニングなどの運動をした時のような、全身の筋肉が多くの酸素を必要としている時に起こる現象です。さらに、病気の症状として息切れが発生することがあり、その場合には平地を歩くだけでも、または日常的な動き(着替えなど)でも息切れが生じる可能性があります。また、呼吸回数が増える、無意識に深呼吸する、息切れ、就寝中に呼吸が苦しくなって目を覚ます、呼吸困難など、息切れの症状は様々な形で現れることがあります。
少しの歩行で息切れ?
息切れの危険度チェック
呼吸困難の深刻度を評価する指標となります。
※Grade2以上の症状が見られる場合は、重篤な疾患の可能性があるため、お早めに受診しましょう。
| Grade0 | 息が苦しくない。 |
|---|---|
| Grade1 | 激しい運動や動作で息切れを感じる。 |
| Grade2 | 急いで平地を歩いたり、緩やかな坂を上ったりした際に息切れを感じる。 |
| Grade3 | 同年齢の方と比べて歩くスピードが遅い。またはご自分のペースで歩いた後に息苦しさを感じ、休憩するために息を整える。 |
| Grade4 | 100ヤード程度歩いた後に息切れを感じ、休憩して息を整える(数分間歩いた後に休憩して息を整える)。 |
| Grade5 | 息が非常に苦しく、外出が難しくなる。もしくは着替えるだけでも息切れを感じる。 |
息切れの原因
- 肺や気管支系疾患、周囲の筋肉に問題があり、呼吸が障害されている
- 貧血による赤血球不足で酸素を運べない
- 心臓や腎臓の疾患による血液循環の低下し、酸素供給が滞る
- 心因性のストレスや肉体の疲労による過換気症候群(過呼吸)
呼吸に重篤な異常が生じると、短時間で生命に危険が及ぶ恐れがあります。原因を正確に突き止め、適切な治療を受けることが極めて重要です。
息切れを伴う疾患
息切れや呼吸困難などを伴う疾患については、下記が挙げられます。
慢性閉塞性肺疾患(COPD)
以前は「慢性肺炎」「肺気腫」として知られていた疾患です。喫煙などで有害な物質を肺に吸い込むことによって引き起こされ、肺にダメージが蓄積し、長い時間をかけて肺機能が低下していきます。放置すると、慢性気管支炎や呼吸不全に陥ることもあります。また、風邪やインフルエンザによる急激な悪化も考えられるため、感染症予防も非常に重要です。
気管支喘息
アレルギーによって気管に慢性的な炎症が引き起こされ、気道の狭窄が起こり、息切れ、息苦しさ、呼吸困難が現れる疾患です。喘息発作時には、「ヒューヒュー」「ゼーゼー」という喘鳴が見られます。
間質性肺炎
肺には、吸気を取り込む小さな袋である「肺胞」が数多く存在しています。間質性肺炎は、肺胞の壁である「間質」に、炎症や損傷が生じる疾患です。肺胞の壁が厚く硬くなることで、血液が肺胞から酸素を効率よく取り込めず、結果として息切れが生じる傾向があります。
肺がん
肺がんが進行すると、肺の大部分で酸素が十分に取り込めなくなり、息切れが生じます。喫煙習慣がある方や、石綿やコールタールを使用する仕事に従事したことがある方は、肺がんのリスクが高いため要注意です。
鉄欠乏性貧血
欠乏症や、消化管出血などによって鉄分が不足すると、酸素を運ぶ赤血球のヘモグロビンが十分に生成されず、全身の酸素不足が発生し、息切れが生じます。そのほか、めまい、全身の疲労感、頻脈などが引き起こされます。
心不全
酸素を含んだ血液を全身に送り出す心臓のポンプ機能が低下することで、全身に酸素不足が発生し、息切れが生じることがあります。そのほか、むくみや湿性の咳、消化器症状、尿量の低下などがみられます。
狭心症
狭心症は、心臓に必要な酸素や栄養を送る冠動脈が、動脈硬化によって狭窄することで引き起こされます。狭心症になると、運動などで多くの酸素が必要になった場合に供給が追い付かずに酸素不足に陥りやすくなります。それにより、圧迫感のある強い胸痛や、息苦しさが現れます。この発作が狭心症発作です。狭心症発作は数分から数十分続き、徐々に症状が和らいでいきます。気になる症状がございましたら速やかに受診しましょう。
不整脈
不整脈とは、脈拍の頻度が高い頻脈、低い徐脈、または乱れたり途切れたりする状態を指します。頻脈は1分間に120回以上となると息切れが起こり、それ以上回数が増えると意識を失う危険性があります。また、1分間に40回以下となる徐脈の場合、息切れに加えてめまいや立ちくらみを引き起こします。
不整脈は発症しても問題がないケースもありますが、心疾患によって起こっている場合は、命に関わる危険な状態のため、速やかな受診が必要となります。
胸膜炎
胸膜に炎症が生じる疾患です。主な原因として、感染症、結核、膠原病、がん疾患などが挙げられます。息切れ、息苦しさ、咳、発熱、胸痛などの症状が現れます。
肺血栓塞栓症
(エコノミークラス症候群)
血管内に生じた血栓が肺の動脈に引っかかる病気です。肥満、同じ姿勢を長時間続ける習慣、外傷、がん疾患、寝たきり、妊娠、ピルの服用などが誘因となることがあります。主な症状としては、息切れ、息苦しさ、強い胸の痛みが挙げられます。
腎不全
腎機能が障害されると、体内の水分が増え、浮腫などの症状が現れる疾患です。胸水や腹水が溜まると、血管内の水分量も増えるため心臓への負担も大きくなります。それにより、息切れを含む多くの症状が出現します。
息切れの検査

- 血液検査
- 呼吸機能検査
- 心電図検査
- 胸部レントゲン検査
- CT検査
- 動脈酸素飽和度
息切れの治療
息切れは様々な原因疾患によって引き起こされる可能性があるため、原因疾患の診断と治療が重要です。症状が軽度の場合は、呼吸の指導や薬の処方などで息切れを和らげています。酸素飽和度が著しく低下しているなど、重症の方には、人工呼吸器の使用や酸素補助などが検討されることがあります。息切れは何らかの疾患の症状として起こる可能性があるため、早めの受診が重要です。
当院では各領域の研鑽を積んだ専門医が在籍しており、患者様の症状に合わせて最適な治療法をご提案いたしますので、お早めにご相談ください。